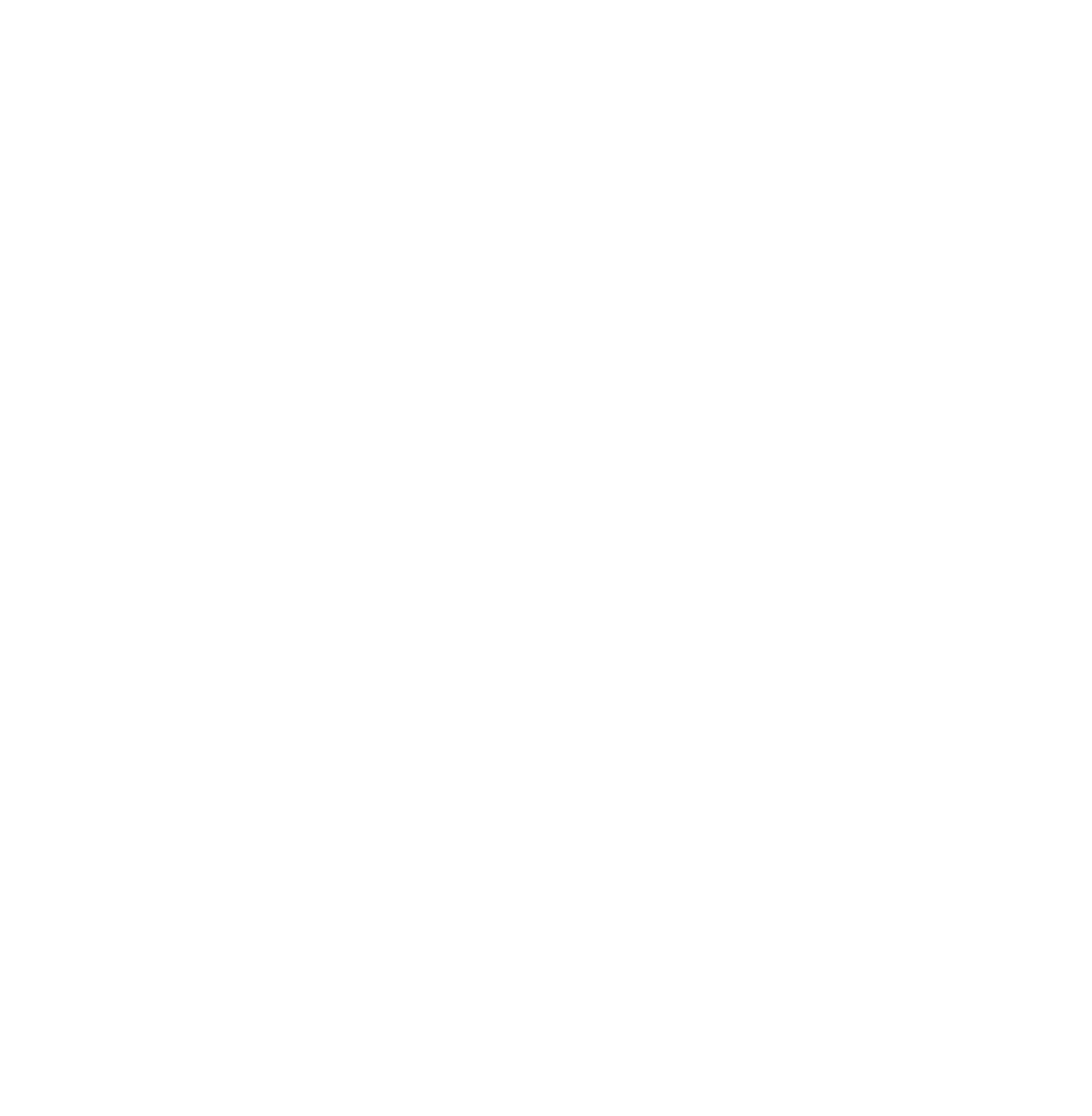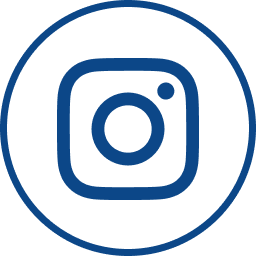2025.12.18
自分らしさを諦めない。近大アンチエイジングセンター市民公開講座に潜入

- Kindai Picks編集部
902 View
近畿大学アンチエイジングセンターが毎年開催する「市民公開講座」。予防医療としてのアンチエイジング効果を科学的エビデンスに基づいて実証することを目指して、市民公開講座の他、スポーツ教室や講演会、研究会を行っています。今回は11月に開催した第37回市民公開講座「自分らしく生きるためのウェルビーイングとアートについて学ぶ」をレポートします。
この記事をシェア
市民公開講座「Well-beingな生き方とは」
講演者紹介
森口 ゆたか(もりぐち ゆたか)
近畿大学文芸学部 文化デザイン学科 教授
専門:ホスピタルアート、アート・コミュニケーション
1986年、シカゴ美術大学大学院彫刻科を修了。以降、国内外の画廊や美術館で精力的に作品を発表。転機となったのは1998年、イギリス滞在中に出会った「ホスピタルアート」。芸術が医療現場の環境を豊かに変える姿に深く感銘を受け、日本でもこの活動を広めようと尽力。帰国後は、日本にホスピタルアートを導入した先駆者の一人として注目され、多くの病院の療養環境づくりに関わる。現在は NPO法人アーツプロジェクト副理事長 として、アートの力で病院環境を温かい場所へと変える活動を続け、患者さんや医療スタッフに寄り添う環境づくりをプロデュースしている。
教員情報詳細
これまでの歩み
売れない芸術家だった頃
私は現在、ホスピタルアート──“療養環境におけるアート”を専門としていますが、もとはずっと美術畑にいました。大学卒業後から何十年も、売れない芸術家として活動していました。関西の小さな画廊や、大阪の地下ギャラリーで作品を発表しても、ほとんど誰も見に来ない。作品も売れない。父も売れない彫刻家でしたので、その「売れない血」をきっちり受け継いだように思います(笑)現代美術という、当時は理解されにくいジャンルを選んだこともあり、美しい花の絵や肖像画のような“売れる絵”とは違い、ほんとうに小さな世界で制作を続けていました。
しかし40歳を過ぎた頃、ふと思ったのです。
「このままずっと、限られた美術愛好家に評価されるためだけに生きていくのだろうか?」
「アートは本当に“これだけ”だろうか?」
そんな焦燥感のようなものが募っていました。
人生の転機:イギリスへの渡航
そんな時、夫が突然「自分は勉強が足りない」と言い出し、20年以上勤めた会社を休職してイギリスの大学院へ行くと言い出しました。まさかの展開で、私も一緒にイギリスへ行くことになりました。最初は「行き先がロンドンだったら素敵!」と思ったのですが、行き先はマンチェスター。大阪の姉妹都市でもあり産業革命で栄えた街ですが、当時は産業が衰退し、大学が主役の街でした。
「マンチェスターで私は何をしよう?」
そんな中、マンチェスターの大学で “Arts for Health(健康のための芸術)” という授業が行われていることを知り、興味を持って訪ねたのが運命の始まりでした。
講座を受けたいと思っていたのに、なぜかその場でスタッフに“採用”されてしまい、気がつけばその活動の一員として翌年予定されていた「療養環境に於けるアートの世界規模のシンポジウム」をお手伝いすることになったのです。
こうして私のホスピタルアート人生が始まりました。
イギリスで見た病院 アートがあたり前にある空間
イギリスの病院を訪れて大きな衝撃を受けました。「ここは本当に“病院”なのか?」
ただ身体を治す場所ではなく、心を癒し、文化と触れ合える空間だったのです。広くて高い天井、自然光が入る天窓、そこに吊るされた大きなモビール作品、写真展や絵画展が常に開催されているエリア、カフェテリアは地域の人もくつろげる空間。
そして一部の病院には “映画館” まである。
病気でもない人が「行きたい」と思うような場所。
ここにアートの力を見ました。
「病院は本来はこうあるべきなのではないか?」
そう気づかされた瞬間でした。
日本でこの活動を伝えたい
イギリスでの経験を経て、私は「日本にもこの活動を届けたい」という強い使命感に駆られました。帰国後、NPO法人アーツプロジェクトを立ち上げ、ホスピタルアートの普及に取り組みました。私が39歳で妊娠し、帰国後に子どもを出産したのですが、まさに娘とホスピタルアートは同時に“誕生”したようなものです。娘の年齢(25歳)が、日本のホスピタルアートの歴史そのものです。
現在では、50か所以上の病院で活動を行い、関西から全国へ広がっています。
アートとは何か?
アートとは何か 語源から考える
「アート」と聞くと、多くの人は絵や彫刻を思い浮かべ、「私、美術はちょっと…」と構えてしまいます。でも、アートの語源を辿ると、「ラテン語 ars(アルス)」「ギリシャ語 techne(テクネ)」となり、「技術」「生きるための技」という意味を持ちます。英語の technique(テクニック) の元でもあります。
つまり本来のアートは、人が生きるために必要な“技”そのもので絵画や彫刻だけを指す言葉ではありません。
日本がアートを“誤解”した時代 ― 明治の西洋化
日本人は古来より、着物・茶碗・花・浮世絵など、生活に深く根付いた美意識を持っていました。しかし明治期、黒船とともに西洋文化が一気に流れ込み、西洋の美術が“高級”“本物”とされ、それまで日本人が愛してきた日常の美は“工芸”として格下にされました。東京藝術大学がつくられ、油絵を教える西洋芸術こそが“正しい美術”とされてきた歴史があります。こうして「アート=西洋の芸術」という誤った価値観が生まれてしまったのです。本当は、家で使う茶碗も、日々眺める花も日本の“アート”。なのに私たちは「美術はわからない」と言ってしまう。
これは歴史が作った認識のズレなのです。
ヨーロッパの医療とアート
医療とアートは本来“同じ場所”にあった
ここからは、医療とアートの関係を歴史の視点でお話しします。皆さんが想像される通り、西洋でも東洋でも、病気や怪我は古くから存在していました。しかし、科学としての医療が整備され、現代のように病院という施設が生まれる前、人々はどこで治療やケアを受けていたのでしょうか。
答えは 「教会」 です。
中世ヨーロッパでは、修道士や修道女が現在でいう医師や看護師の役割を担い、病人や傷ついた兵士、貧しい人々を教会にかくまい、治療やケアをしていました。
では、教会には何があったでしょうか。
・マリア像
・キリストの磔刑像
・ステンドグラス
・聖歌、宗教音楽
つまり、教会=医療(ケア)+アート+宗教が同居する場所 だったのです。医療の現場には、もともと自然にアートが存在していました。科学が発達し医療が独立していくなかで、「医療」と「芸術」は別々の領域へと分かれていっただけなのです。
私がイギリスでホスピタルアートに出会ったとき、感じたのはまさにこれでした。
「これは新しい活動ではなく、元に戻ろうとしている“先祖返り”なのだ」
病院が発展する過程でこぼれ落ちてしまった“文化”や“心のケア”を、アートが再び拾い集める役割を担っている。私はそのように考えています。
イギリスのホスピタルアートは“国全体の活動”
ホスピタルアートはイギリスで1960年代から発展し多くの団体が生まれ、いまや国を挙げての活動となっています。イギリス全土を9つのブロックに分け、それぞれにホスピタルアートの推進組織が置かれています。これら地域組織の上に位置するのが、日本の文化庁にあたる Arts Council England(英国文化庁)。
各グループが1年間の活動報告を提出し、Arts Council England から税金の一部が支給され、次年度の活動に充てる仕組みになっています。
また、日本では考えにくいのですが、イギリスでは医療とアートに関心を持つ議員が”党派を超えて”集まり、All-Party Parliamentary Group for Arts, Health and Wellbeing(アート・健康・福祉のための超党派議員連盟)として政策提言を行っています。
彼らがまとめた提言書は辞書のように分厚く、“芸術が国民の健康とウェルビーイングに不可欠である”という内容が数多くの実例とともに示されています。
イギリス社会が「アートを病院に入れよう」とした理由
イギリスは階級社会で、歴史的にアートは王侯貴族のためのものでした。しかし1960〜70年代の学生運動など社会の変革を背景に、
「アートはお金持ちだけのものではない」
「貧しい人も、病気の人も、誰もが文化的な豊かさを享受すべきだ」
という考えが広まりました。
その結果、アートを病院に取り入れることが“公共の福祉”として認識され、国を挙げてのプロジェクトへと発展していったのです。
アートに満ちた病院
私が20年前に訪れたロンドンの Chelsea and Westminster Hospital(チェルシー・アンド・ウェストミンスター病院) は、まさに驚きの連続でした。● 世界最長クラスの巨大モビール
病院ロビーの天井は非常に高く、太陽光が降り注ぐ天窓があり、そこから全長24メートルを超えるモビールが吊り下がっています。
● 病院内に「アートオフィス」
日本の国立国際美術館の学芸員が9人だった時代に、一つの病院に5人のキュレーター(学芸員)が常駐 していました。
● なんと“映画館”まで
その病院には小さな シアター(映画館) があり、入院患者も外来患者も自由に映画を見ることができます。
「病院で映画が観られるなんて!」と驚かれる方も多いと思います。
しかし、退院間近で元気になってきた患者さんにとっては、退屈な病院生活の中で映画は大きな楽しみになります。
通院時の待ち時間が長くても、映画や写真展があれば心が軽くなります。
こうしたアートの力で、病院が「行きたくない場所」から「行けるなら行きたい場所」 へと変わるのです。
日本の病院とアート
日本の病院との“歴史的違い”
日本の病院の多くは「○○大学医学部附属病院」という形が多いです。つまり、医学の研究機関として病院を運営しています。
その結果、歴史的に医療の発展が第一で、患者はそこに“呼ばれる存在”という構造がありました。
対してヨーロッパでは、医療は宗教施設とともに発達し、人をケアする文化と芸術がずっと寄り添っていました。
だからこそヨーロッパの人々にとっては「病院にアートがあるのは当たり前」という感覚なのです。
日本での実践:全国50か所を超える病院でホスピタルアートを導入
イギリスでの活動に影響を受けて帰国した私は、日本でも必ずホスピタルアートを広めなければならないという思いに駆られ、2002年にNPO法人アーツプロジェクトを設立しました。おかげさまでメンバーにも恵まれ、メディアにも取り上げていただいたことで、活動は徐々に広がり、最初は関西での取り組みでしたが、現在では全国50か所以上の病院 でホスピタルアートを実践しています。四国こどもとおとなの医療センターでの大規模プロジェクト
2013年、香川県善通寺市に「四国こどもとおとなの医療センター」が開院しました。この病院の外壁から内装、フロア全体の色彩計画、中に設置するアート作品に至るまで、私たちのNPOが総合的に担当させていただきました。
● 小児科総合受付の空間デザイン
小児科総合受付には、元々四角い鉄筋の柱が立っていました。それをアーティストが“樹木のようなオブジェ”として造形し、空間の主役へと変えました。頭上には、子どもが描いた絵をもとにアーティストがシルエット化したデザインを組み合わせ、天井から吊り下げています。ちょうど森の中にいるような空間です。
● 1時間ごとに音楽が流れる「からくり時計」
さらに、天井部分には1時間ごとに違う音楽を奏でるからくり時計が埋め込まれています。病院の中で時間が単調に過ぎていくのを、少しでも楽しいリズムに変えるための仕掛けです。
● 子ども専用の“絵本の家”
受付の横の赤いスペースは子ども専用の図書館です。大人は通れないほど小さな入口になっていて、中には絵本がずらり。子どもたちにとって「ちいさな秘密基地」のような空間になっています。
● フロアごとのテーマカラーで迷わない病院へ
多くの方が病院で迷った経験があると思います。どの階で降りても景色が似ていて、“どこに来たのかわからない”と不安になることがあります。
そのため、各階に違うテーマカラーを設定し、エレベーターが開いた瞬間に「あ、この色だから○階だ」と直感的にわかるようにしました。
アートは、ただ鑑賞するためだけでなく、「道案内」「安心感の提供」 という実用的な役割も果たします。
病院の壁に“幸せの引き出し”を 誰でも取っていいアート
四国の病院には、もうひとつ大切な仕掛けがあります。壁の一部に「家の形の小窓」が並び、そこにアーティストの作品やボランティアの手作り作品、患者さんが寄贈した詩などが入っています。 この小窓のアートは “誰でも自由に持ち帰ってよい” という仕組みです。
ボランティアの方々が編んだ小さなあみぐるみが入っていたりします。ある患者さんが、そこで見つけたあみぐるみに「ガン太」と名付け、「僕ガンなんでね、ガン太にしました」と大切にしていた姿が印象的でした。
ここには高価な美術品はありません。必要なのは、患者さんの心に寄り添い、入院生活を少しでも楽しくする“あたたかいアート”なのです。
近畿大学病院での実践 小児科の壁画制作
近畿大学病院でも2009年から継続してホスピタルアートの活動を行っています。小児科の壁画制作では、当時入院していた5歳の女の子たち(小児がんの患者さん)が参加してくれました。病院のスタッフや学生と一緒に筆を持って壁に絵を描く時間は、本当に生き生きとしていて、病気の子だと忘れてしまうほど元気でした。学生に向かって「お姉ちゃん、違うって。緑はこっち!」と指示を出す姿は、まるで小さなアートディレクターでした。
完成した壁画は、小児科の入り口を明るく彩り、いまも多くの人を迎え続けています。


ホスピタルアートの本当の役割とは?
「ホスピタルアート」と聞くと、“病院を美しく飾るためのアート”と思われることが多いですが、それは一部にすぎません。「アートは“人間らしさ”を取り戻すために必要なもの」
入院すると患者認証タグをつけられ、身体は毎日測定され、数値で管理される存在になります。もちろん医療安全のために必要なことですが、人間は測定されるために生きているわけではありません。
アートは「その人がどんな人生を歩んできたか」「どんな喜びや悲しみを抱えているか」「何に心が動くのか」など“数値化できない部分”を回復してくれます。個性や尊厳を取り戻すきっかけになる。だからこそ病院にはアートが必要なのです。
医学はサイエンスに基づくアートである
医療とアートの“分岐”と“再会”
中世ヨーロッパの教会には、病人・けが人・貧しい人が集められ、修道士や修道女が彼らのケアを行っていました。その場所には常に、マリア像やキリスト像、ステンドグラス、聖歌やオルガンの音色といった“アート”が自然に存在していました。病院という施設が生まれるよりも前から、医療とアートは同じ空間にあった という歴史があります。しかし科学が発達し、医学が体系化され、大学という研究機関ができ、医療が高度化・専門化する過程で、医療と芸術はいつの間にか別々の道を歩むようになりました。
「ホスピタルアート」は新しい試みではなく、むしろ“先祖返り”。
医療が発展するなかで失った文化的・精神的なケアを、アートが再び病院へ呼び戻しているのです。
「医学はサイエンスに基づくアートである」
19〜20世紀にかけて活躍した医学者ウィリアム・オスラー(William Osler) の名言としてこのようなものがあります。“Medicine is a science of uncertainty and an art of probability.”
「医学は不確実性の科学であり、可能性のアートである。」
ここでいうアートとは絵画や彫刻ではなく、“人間の生きる術としてのアート”のことで、つまり医学とは、科学(サイエンス)を基礎にした“アート(技)”であるという考え方です。
医療とは本来、患者の心と身体を癒すための総合的な技術であり、科学だけでは完結しない側面がある。だからこそ、「科学にならない“心の部分”こそ、アートが担うところ」であると考えています。
病院の中で失われやすい「人間らしさ」
入院すると、私たちは“患者”という役割を負わされます。手首には患者認証タグをつけられ、朝は体温と血圧を測定し、数値によって管理される日々。もちろんこれは医療安全のために必要な手続きです。
しかし、私たちは体温と血圧のような数値だけで成り立つ存在でしょうか?
生きてきた経歴も、経験してきた喜びも、大切な人との思い出も、趣味や好みも、心の動きも――それらは数値にはなりません。しかし確実に「その人を形づくる要素」です。
医療が発展して定量化が進むほど、その“人間らしさの部分”が見えづらくなります。
医療の場にアートがあることで、診る側・診られる側の関係が柔らかくなり、場の空気が和らぎ、“その人自身”が少しずつ浮かび上がってきます。
医師の大切な役割とは何か
日本のホスピタルアート推進者である日野原重明先生(故)のこんな言葉があります。「医師の大きな仕事は、患者の痛みを“心の側面”から癒すこと。」
「医学とはサイエンスの上に成り立つアート(技)である。」
オスラーと同じように、医師は数字だけを診るのではなく、“心の痛み”や“人間らしさ”を見るべきだという提言です。
しかし現代の医療現場では、電子カルテや検査データを優先せざるを得ない状況も多く、医師が患者の顔を見る時間が減っています。
ー昔は聴診器を胸に当ててくれた。
ー顔を見て話してくれた。
ーそこから“心の状態”も汲み取ってくれた。
現代医療の効率化の代償として、人間的なコミュニケーションが失われている側面があります。
だからこそ、医療の空間にアートが入ることで、病院のコミュニティのあり方が見直され、患者さんも医療者も“ただの人間”として向き合う空間を復活することができるはずです。
病院を楽しく、美しく、ハッピーな場所になるように、アートの力で変えていきましょう。
近畿大学は、近畿大学奈良病院、近畿大学奈良病院薬剤部、薬学部、薬学総合研究所、農学部食品栄養学科、健康スポーツセンターなどが中心となり、文部科学省「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」の助成を受けてアンチエイジングセンターを設置しました。専門分野が異なる複数の研究者が分野横断的に連携し、3つのC【Check(加齢マーカーを指標とする診断)、Care(健康指導・栄養指導)、Cure(長期スパンでの支援)】を実践し、予防医療としてのアンチエイジング効果を科学的エビデンスに基づいて実証することを目指しています。
近畿大学アンチエイジングセンター Webサイト
取材・執筆:Kindai Picks編集部
この記事をシェア