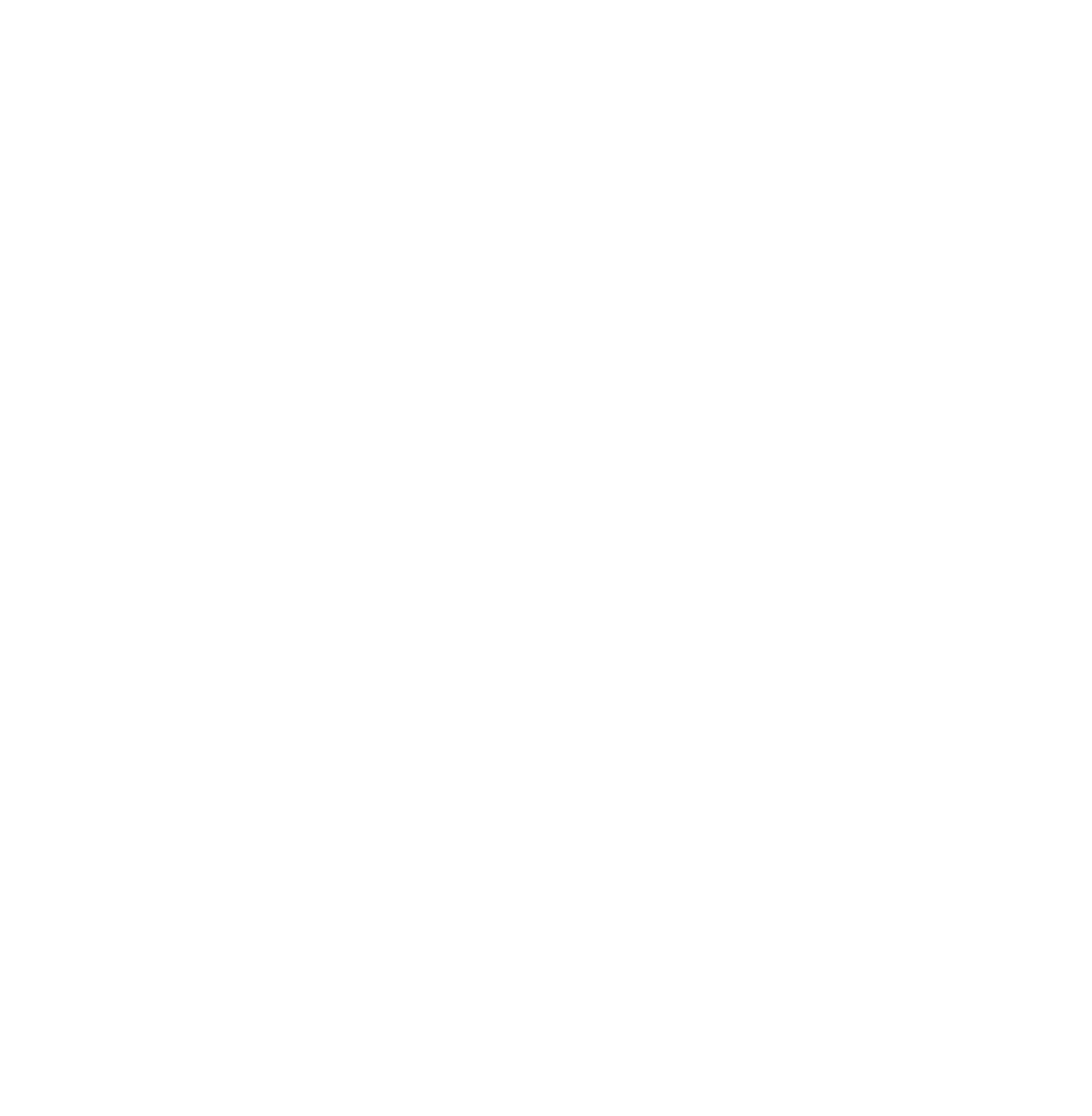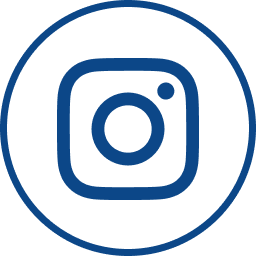2022.07.21
ドライブ・マイ・カー共同脚本・大江崇允さんインタビュー「演劇を学ぶのも、映画をつくるのも、人間を知りたいから」

- Kindai Picks編集部
2893 View
映画『ドライブ・マイ・カー』。第74回カンヌ国際映画祭脚本賞をはじめ、世界各国で10以上の栄えある賞を受賞した作品です。監督である濱口 竜介さんと共同脚本を手がけた大江 崇允さんは、近畿大学 文芸学部の卒業生。今回、文芸学部の学生と教職員が企画開催する文芸フェスタにて大江さんが講演されると聞きつけ、独占インタビューをご依頼。「どんなふうに学生生活を過ごしましたか?」「卒業後も創作活動を続けていくには?」創作の世界を志す学生たちへのメッセージをお伺いしました。
この記事をシェア

1981年大阪府出身。2004年、近畿大学文芸学部芸術学科 演劇・芸能専攻(現:舞台 芸術専攻)卒業。近畿大学で舞台芸術を学んだ後、2003年に「旧劇団スカイフィッシュ」を旗揚げし、演出家や俳優として舞台作品に携わる。その後、映画制作を始め、監督 ・脚本家として活動。初監督作『美しい術』(2009)でCINEDRIVE2010監督賞を受賞、2 作目となる『適切な距離』(2011)は第7回CO2グランプリほか国内外で評価を受けた。短編『かくれんぼ』(2012)は第7 回大阪アジアン映画祭インディ・フォーラム部門に出品された。そして濱口竜介監督との共同脚本『ドライブ・マイ・カー』が、第74回カンヌ国際映画祭で日本映画としてはじめて脚本賞を受賞。
一人では描ききれなかった世界に到達できる? 共同脚本の可能性

インタビューには、盛 加代子先生(文芸学部 芸術学科 舞台芸術専攻)が同席。質問もしていただきました。
──大江さんが共同脚本を手がけた『ドライブ・マイ・カー』は、カンヌ国際映画祭では脚本賞はじめ、他3つの独立賞を受賞、アカデミー賞では国際長編映画賞を受賞しましたね。改めて、おめでとうございます。
村上 春樹さんによる短編小説『ドライブ・マイ・カー』(『女のいない男たち』収録)。妻を失った男の話を、濱口 竜介監督が映画化。
大江:ありがとうございます。ぼくは今日「ドライブ・マイ・カーの人です」と紹介していただきましたが、『ドライブ・マイ・カー』はあくまで濱口竜介さんの監督された映画で、ぼくは共同脚本として参加しただけです。ですので、映画のすべてを知っているわけではなく、その角度からしかお話はできないかと思います。
今回は、濱口さんがここまで連れてきてくれました。今後は、ぼくもがんばっていきたいです。

──以前から、濱口さんと交流があったんですか?
大江:直接会うことはなかったんですけど、インディペンデント界隈で映画をつくる中で、お互いに存在は知っていました。
──そこから、どういう縁で?
大江:濱口さんが『ドライブ・マイ・カー』を映画化するにあたり、「演劇に詳しい脚本家を探している」と。ぼくが以前からお世話になっている山本晃久プロデューサーから声がかかりました。
──大江さんは、脚本ではどの部分を手がけましたか?
大江:映画の舞台は、もともと韓国でした。そこで濱口さんと現地に行き、シナリオ・ハンティング※をしました。
※シナリオ・ハンティング:脚本や台本を製作するための取材
それから、映画冒頭で、主人公である家福の妻・音(おと)が読み上げる「やつめうなぎ」のストーリーの原型みたいなものを書きました。これは原作をもとにして※、少し変更を加えました。そこにさらに濱口さんが改稿して、音の語る物語ができました。
※『女のいない男たち』に収録された短編小説『シェエラザード』では「私の前世はやつめうなぎだったの」から始まる場面がある。

戯曲『ゴドーを待ちながら』(サミュエル・ベケット作)から一場面を取り入れたのも、大江さんの提案から。
──共同で脚本を書くというのは、新鮮だなと感じました。
大江:映像ではそんなに珍しくはないと思います。“チーム・ライティング”とでも呼べばいいのかな。チームによってつくり方は異なりますが、今回の場合は濱口さんが脚本を書き、山本プロデューサーとぼくの3人で読み合わせ、また濱口さんが書き進める。その繰り返しです。

──濱口監督はカンヌ国際映画祭の受賞スピーチで、大江さんについてこう話していましたね。
大江さんと僕の関係は奇妙なもので、僕にひたすら書かせるタイプの脚本家。いつも読みながら、“本当に素晴らしい。このままやりなさい” と言ってくれました。この作品は、3時間近くあり壮大な物語。彼がずっと励まし続けてくれたから、この物語を最後まで映画として書き切ることができたと思っています。
大江:脚本家は、一本の映画の脚本を、何度も繰り返し読んで、書き直して形にします。どれだけ優れた人間でも、一人の脳だと必ず限界があります。一人では描ききれなかった世界にいかに到達できるかが、チーム・ライティングの可能性かもしれません。
その時に欠かせないのが、いいチームとの出会い。「人とつくる楽しさ」は、演劇に通じていますね。
──学生の中には、「自分一人での表現を追求したい」という人もいるかと思います。大江さんには、その気持ちはありませんでしたか?
大江:演劇も映画も、一人ではつくれないじゃないですか(笑)。そこが面白い。ぼくがもし「みんなでつくるのは窮屈だ」と感じていたら、もっと別の表現方法があったと思います。

脚本は、俳優の体から出る言葉。だからコミュニケーションが欠かせない
──共同で脚本をつくる上で、大切にしていることってありますか?大江:コミュニケーションですね。
もしみなさんが共同で芝居の脚本をつくるとして、パートナーから「今ひとつだな」という脚本があがってくることだってあります。その時にあれこれ言いたくなると思うんですけど。
ぼくは筆者がたくさんの努力と時間をかけて書いた脚本に、まずは敬意を持つようにしています。次に、場と相手を見ます。そして、10個言いたいことがあるうちの「どうしてもこれは」というたとえば3個だけ伝える。

「でも、“人を傷つけないように”とか“人との製作にはなれあいがつきもの”という話ではないんです」と大江さんは補足。
大江:一つの演劇作品という「全体」において、自分は「一部」なんですよね。だから、「こうしたら面白い」っていう自分なりの100点満点があったとしても、それが必ずしも面白い作品に繋がるとは限らなくて。ぼくの経験上は、むしろ、逆をいくことが思わぬ120点を生んだりします。
──改めて大江さんにとって、「脚本」ってどういうもの?
大江:ぼくは「俳優自身の体から出た言葉」だと、思います。
キャラクターが台詞を口にして、初めて脚本は誰かに届きます。いくら頭で考えても、書かれただけの状態なら意味がない。脚本って文学ではないので。俳優が発語することをイメージしています。
「仲間を探したいから毎日大学にきて、演劇を学びました」

──大江さんが入学したのは、商経学部だったと聞きました。
大江:そうです。2年生までは、商経学部にいました。でもどうしても映画やりたくて。当時、文芸学部 舞台芸術専攻に移ったら映画も一緒に学べることを知って、転部したんです。「もう時間がない。まずいぞ」と、当時はめちゃくちゃ焦ってましたね。周りのみんなが4年間学べるのと違い、ぼくには卒業まで3年しかなかったので。今思うと、表現ならなんでも良かったんでしょう。学ぶうちに、演劇が面白くなってきたんです。
──大学で未来の仲間を探そうとしていたんでしょうか?
大江:そうです。俳優コースに通っていて、だんだんと先輩の芝居に俳優として出演したり、スタッフとして手伝うようになって。
──卒業後はどんな活動をしていたんですか?
大江:2003年に仲間たちと「旧劇団スカイフィッシュ」を立ち上げました。当時はとにかく、表現の世界に自分の居場所を見出したかったんです。演劇の世界で自分の居場所を探していたので、思いつく限りのことを色々と試していました。
──演劇の道を続ける可能性もありましたか?
大江:そのまま縁が広がっていたら、今も続けていましたね。たまたま運良く映画をつくることで縁が広がったから、今も続けています。

──俳優として映画に初出演したのが、『歩行する季節』(2006)ですね。
大江:監督は、近畿大学の2期後輩にあたる戸田彬弘くんでした。
──同じく戸田さんが監督する『花の袋』(2008)で、映画の脚本家としてデビューしました。
『花の袋』は、奈良県の後援を得て制作した、高校生8人の1年間を描いた青春群像劇。
大江:そんな大層なものではないです。一緒に映画をつくる一人としていただけです。ぼくは、肩書きは自分ではなく人が決めるものかなと思っていて。当時も今も、「脚本家」としての自覚はないんです。
──脚本の書き方は、誰かに教わったのですか?
大江:独学というか、手探りでしたね。ビデオ屋さんで、当時邦画ランキング1位だった『ハチミツとクローバー』をレンタルして観ながら、台詞を書き起こしていったんです。そうすると、映画の構造が少しだけわかりました。
──次回作の『美しい術(すべ)』(2009)では、脚本と監督をつとめましたね。
大江:『花の袋』に携わったから、次は監督してみたという流れだったと思います。
──そして、『適切な距離』(2011)ですね。
大江:実は、この映画の舞台は近畿大学なんです。演劇を学ぶ学生が、会話のない母親とお互いの日記を読み合うことでコミュニケーションを図る映画です。
大学時代の仲間たちとつくった作品。共同脚本は菊池開人さん。
──『適切な距離』は、演劇を映画に取り込み、舞台裏を見せることで、観客との共犯関係をつくり出していますよね。『ドライブ・マイ・カー』に通じる視点※を感じました。
大江:はい。そういうご意見をいただくことはあります。
※『ドライブ・マイ・カー』では、チェーホフの演劇作品『ワーニャ叔父さん』上演に向けて、俳優たちが稽古する場面がある。
ー言わば、大学時代の経験や繋がりが『ドライブ・マイ・カー』に繋がった、と。
大江:それはあるでしょうね。でも、誰かと作品をつくるときに、もちろん実績なんかも大事なんでしょうが、「この人面白そう」と思ってもらえることが幸せじゃないですかね。ぼくが『ドライブ・マイ・カー』の現場に入れた理由も、「大江とつくったら面白そうだな」と思ってもらえたからだとしたら、幸せです。

ちなみに『適切な距離』には盛先生も出演。「学生たちをこっぴどく叱る先生役なの(笑)」
「たぶん、俳優になるために演劇を学ぶわけではなくて」

──大江さんが、授業で得たことは?
大江:すべての芸術に通じる「芯」ですかね。それを学んだのは、「ルコック・システム※」の授業でした。クラシック音楽も、美術館の絵画も、ルコックを学んだ後では、それまで見えなかった面白さが理解できるようになった気がします。そうして表現の世界で生きるための術を学んだから、ぼくは今ここにいるのだと思います。
※ルコック・システム:フランスの演劇教育者、演出家、俳優だったジャック・ルコックが生み出した、俳優教育理論
──それは、どういう授業だったのでしょう?
大江:転部して最初のうちに受けた授業で、演出家の大橋也寸(おおはし やす・近畿大学名誉教授)さんに「外に出て、動物を見てくるように」って、言われたんです。
次の授業で、「ハトはどんな風に翼を広げていた? 再現してみて」と。なんとなく肩の真横で腕をパタパタしてみるんですけど、彼女は「もっとちゃんと見なさい」って。もう一度ハトを見ると、羽はもっと背中寄りについていることに気づいて。

今も「アラスカに吹く風の音を口で表現する」というような授業があるのだとか。「最初は有声音の“ブー”とか“サー”とか。そこから無声音をあれこれ試して、どんどん変わっていくの」と盛先生。
大江:そういう視点でいると、ずっと面白いんですよね。たとえば八戸ノ里駅から乗った電車で、向かいのシートに座っている5人組を見たとして「話の中心になる人って、座る場所が決まっているよな」という構図というか、人の無意識の配置に気づいたり。いつもの風景が、はじめて見る世界みたいで。
──なるほど。高校までの勉強って「受け身で教わる」ことが多かったと思います。大学で、大江さんはどう学んだのでしょうか。
大江:大橋さんから「何かを教わった」という感覚はないんです。かわりに、見ていましたね。「彼女には、演出家として演劇における明確なジャッジの基準がある。それは一体なんだろう」と。
──どうして、大学で演劇を学ぶんだと思いますか?
大江:同期の話なんですけど「ルコック・システムのおかげで就職できた」と話していて(笑)。採用試験にディベートってありますよね。その場で「この人は今こういう話の流れを無意識につくっている」といったふうに人を見る目だったり、「ずっと一人の人が早口で話し続けているから、ゆっくり一言挟んでみよう」という演出的な視点が浮かんだりしたと。
たぶん、俳優になるために演劇を学ぶわけではなくて。人と人が関わり合う社会のありとあらゆる場で、学んだことは活きる。人間を学ぶ時間だったわけですから。
そうやって捉えると、大学の4年間は、すごく実りのある時間になると思うんです。
脚本は、俳優の体から出る言葉。だからコミュニケーションが欠かせない
ここからは、「文芸フェスタ」での講演会における学生からの質疑応答の一部を紹介します。
当日は、定員の120人を超える学生が出席し、次々と質問。在学中の大江さんを知る林公子先生と盛先生が聴き手をつとめました。
学生:あのー、大江さんが先ほど、さらっと「大学卒業後に映画をつくりはじめた」と話していたんですけど……それってどういうことですか?! わたしも映画をつくりたいけど、どうやったらいいかわからなくて。
大江:そうですよね(笑)。今だから「さらっ」と話せるんですけど。当時は……興味のありそうな人たちをネットで募集かけてみたり。東京の映画製作現場で活動している大学の後輩と連絡を取ってみたり。そうやって少しずつ繋がっていきました。
いざ映画をつくり始めた時は、カメラアングルが全然わからなくて。演劇をしてきたぼくには「寄り」とか「引き」という概念がなくて。ほんとうに手探りでやってきたという感じ。でも、根本にあるのは「映画つくりたい」っていう興味だと思います。

「シネアスト・オーガニゼーション大阪(CO2)のワークショップなどで相談に乗ってもらう方法もありますよ」と大江さん。
学生:大江さんは、演劇で食べていくことがこわくありませんでしたか?
大江:こわかったですよ。食えない前提でやってました。実際、30過ぎまでバイトしてましたし。……あー、ちょっと待って、ちゃんと答えられてないですね、もうちょっと考えます。
……もしあなたが「演劇で食べていきたい。でも、こわい」という悩みを持っているのなら、一度就職してみては? それでも思いが抑えられなくなったら、つくらざるをえないと思います。
学生:なるほど……就職してみます!

大江:人生は長いと思うんです。演劇って40歳を過ぎてから始めて、いきなり時の人になることもある。
それは芝居が、人間をあつかうものだからです。きちんと日々を生き抜いてるだけで、芝居も勝手にうまくなっていたりする。だから、就職しても自分次第で戻ることもできるかなって。実際、そういう同期もいます。今もいきいき俳優やってますよ。表現って、仕事というより、ぼくは生き方かなって考えてます。

たとえジャンルが違っても、学んだことを活かす生き方はたくさんある

講演会の終盤、先生より「最後にもう一人だけ。どうしても質問したい学生は、いますか?」という声かけがありました。そこで一人の学生が、「ぼくは1年生です。今日、この会場にもたくさんいる1年生のみんなにメッセージをください」と手を挙げました。
大江:偉そうなことは全然言えませんが。そうですね、ぼくが大学で学んでいた時は「バイトだから」って稽古を休んだ人から、演劇をやめていきました。これは「バイトをするな」と言いたいのではなくて、つまり無茶苦茶に演劇やった人間が残ったんです。だから、たくさん芝居を学んでください。たくさん芝居を見てください。そして、たくさん芝居をしてください。そうやって、演劇を精一杯楽しんだらいいと思います。
でもその結果、演劇、やめてもいいんです。やめるって、悪いことじゃない。だって演劇で学んだことを活かす場は、この世界にいっぱいあるんだから。

「映画も演劇も、人とつくることに楽しさがある」と繰り返していた大江さん。時おり「ちゃんと伝えられているかな」と確かめながら、学生の質問に答える様子は、90分間の講義を学生たちと一緒につくっているようでした。
インタビュー終了間ぎわに「今後つくりたい作品は?」と質問すると、「今は、100年前につくられた映画をすぐに観ることができる時代になっています。100年後の人間にも、選ばれる映画をつくりたい」と話してくれました。今後の作品が楽しみです。
写真:平野明
取材・執筆:大越はじめ
編集:人間編集部
この記事をシェア