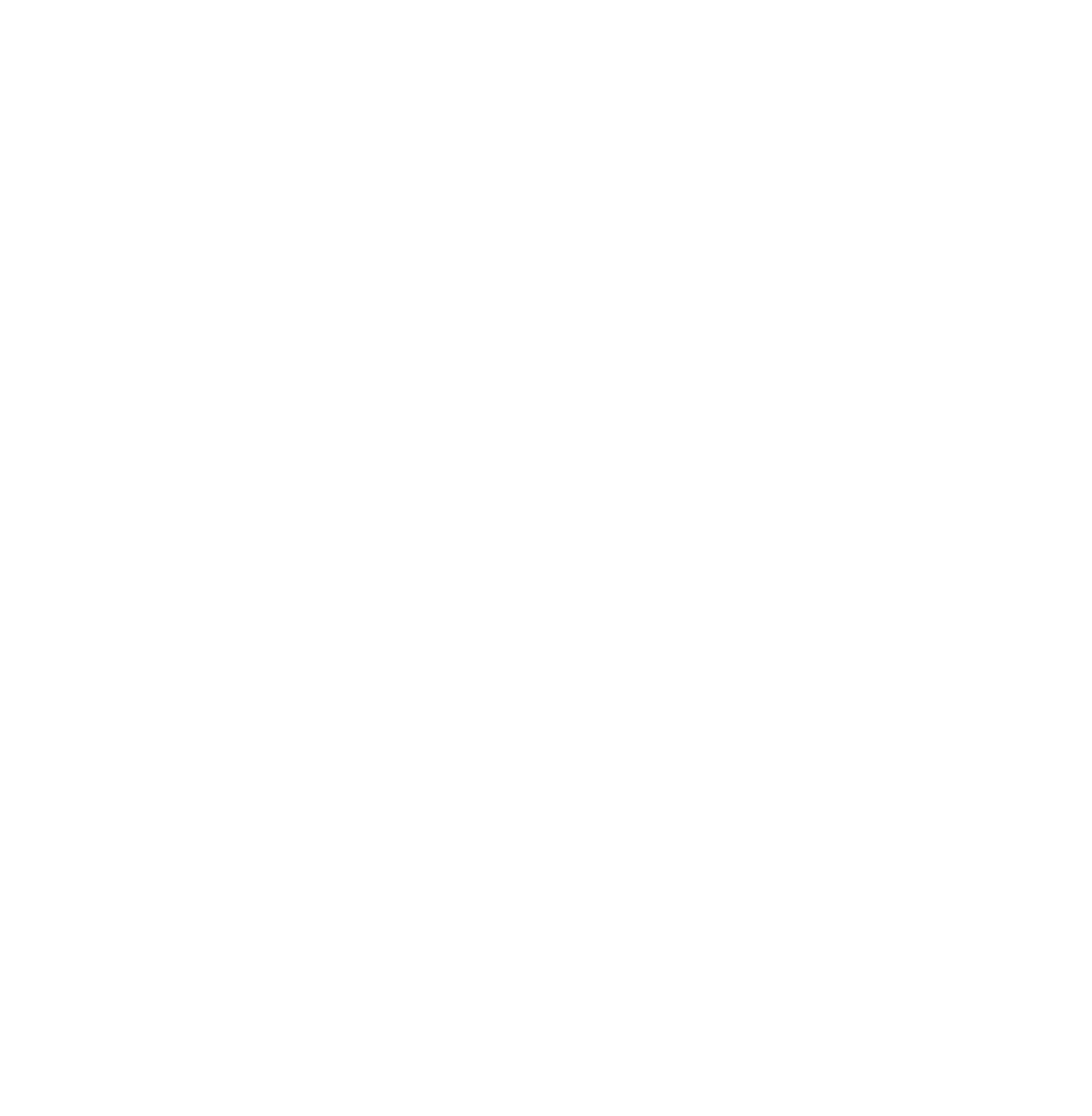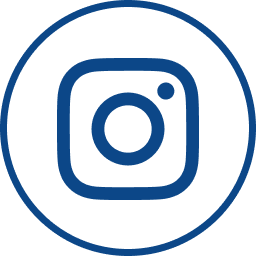2016.11.21
ウナギ味の近大発ナマズ 開発者が「必ず儲かる」と言い切る訳

8568 View
近畿大学が絶滅が危ぶまれるニホンウナギの代替品として開発した「近大発ナマズ」について、作家の山下柚実氏がその開発ストーリーと巧みなビジネス手法に迫った。
*本記事は SAPIO 2016年9月号(小学館) に掲載された記事です。
この記事をシェア
新たな研究や技術を使ってビジネスを生み出し世界で勝負するアベノミクス「第3の矢」の柱の一つに「ベンチャーの加速」が掲げられた。大学も例外ではない。
今、大学発ベンチャー企業の創出に拍車がかかっている。育成ファンドの規模は1年で2.6倍にも膨らみ、1000億円に達する勢いだ(日本経済新聞2016年1月11日)。
では、成果はどうだろうか?例えばミドリムシの大量培養技術で食糧・エネルギー問題に挑戦する(株)ユーグレナは東大発ベンチャーの雄。売り上げも株価も急上昇し、成功事例として熱い視線が注がれている。
しかしその一方で、苦戦も目立つ。起業しても多くは黒字化できていない。米国のように短期間でビッグビジネスに成長した大学発ベンチャーは、日本ではいまだ見かけないのが現実だ。
そもそも教育・研究機関である大学は経営の素人。いくら研究室で新技術が生まれても、儲かるビジネスに育てるのはたやすいことではない。
そんな中、気を吐く大学がある。志願者数日本一の人気を集める近畿大学が、「近大マグロ」に続く新ビジネスに着手した。数々の大学発ベンチャーの苦戦を尻目に「必ず儲かる」と言い切る大学教授は、その胸にどんなもくろみと勝算を秘めているのか。

「ナマズが空を飛んだ!」
6月、そんなニュースがお茶の間を賑わせた。格安航空会社ピーチ・アビエーションが機内食の夏メニューとして「近大発うなぎ味のナマズごはん」の提供を始めたのだ。約700食の数量限定だが、「社内でウナギに似ていると評判になり導入を決めた。新しい驚きを与えたかった」とピーチは導入の動機を語る。
資源枯渇が危惧されるウナギの代わりとなる、「蒲焼き」の提案だ。近大でその開発に力を注いできた中心人物が、同大世界経済研究所の有路昌彦教授(41)。
「ウナギの絶滅危機をうけて、養殖業者や蒲焼き業者から『代わりの魚を探してほしい』と相談されたことがきっかけでした」と動機を振り返る。有路氏は長年養殖魚の研究に携わってきた専門家。依頼を耳にした時、ひらめいた。
「かつて琵琶湖で食べたナマズがうまかった。一番適している、と直感しました」
味と共に、市場競争で勝てる低コストの食材でなければいけない。そこで他にも多数の魚を検証してみた。
「ドジョウ、マス、フナ、ブラックバス、ブルーギル……20種類以上を片っぱしから獲っては蒲焼きにしました。中にはまずくて食べられないものもありましたね。その上でやっぱりナマズだ、との結論にたどり着いたんです」
しかし、全国からナマズを取り寄せて蒲焼きにしてみると、ショックを受けた。
「おかしい。泥臭くて食べられないんです。果たしてナマズは最適なのか?琵琶湖のナマズはたしかにうまかった。しかし、他のナマズはまずくて食べられない。理由は何なのか。そしてやっと気付きました。ナマズの味は水とエサによって大きく左右されるのではないか、と」
泥臭くなくウナギのように脂の乗った「蒲焼き」向きのナマズを育てるのは、実は容易なことではない。水質・温度、エサの配合といった細かな技術が必要です、と有路氏。
「300種類の中から7種類までエサを絞り込んでいきました。弾力感を出すために甲殻類の割合を多くするといった配合方法も解明し、まず厚めの肉を作った上で脂を乗せていく手法を編み出しました。エサの配合、与えるタイミングも含めた独自の養殖技術を確立していくためには、時間がかかりました」
エサの配合が決まったのは2015年2月。研究開始から6年の歳月が流れていた。ウナギ味のナマズ生産が現実味を帯びてきた。卸値も大きく下げることができた。
では、味はどうなのか?本当に、鰻重に並ぶ満足度を消費者に提供できるのか?試食を開始すると、69%が「また食べたい」と回答。上々の評判を受け、有路氏自らも出資して養鰻業者と共に日本なまず生産株式会社を設立、量産化へと踏み出した。マーケティングや水産加工・流通等を手がける(株)食縁も起業し有路氏は社長に就任。営業で各地を駆け回った。
そして今年の土用の丑の日。いよいよ「近大発ナマズ」が新たなフェーズに入った。イオン等大手スーパーで世界初の「近大発ナマズの蒲焼き」販売が始まったのだ。それまでは料理店や機内食での販売が主だったが、庶民の食卓へ一歩接近することに。
「蒲焼きで販売するには別のハードルがあり、カットの仕方から焼き方まで40もの工程で工夫を重ねて、やっとスーパー店頭での販売にたどり着きました」と有路氏は感慨深げ。それでもまだ、バンザイと叫ぶわけにはいかない。
「近大発ナマズ」はそのインパクトからテレビやネットで大反響を呼び注文が殺到。今年は100トンの出荷が目標だが、実は20トン程しか供給できていない、という。原因は突然膨らんだ需要に対する、稚魚の決定的な不足。
「その問題も1、2年のうちにメドを付けます」と有路氏は苦笑しつつ「大丈夫です」と自信を見せた。
数々の大学発ベンチャーが苦戦する中、「必ず儲かる」と有路氏が言い切るのはいったいなぜなのか。
「実は北米、アジア、アフリカと世界各地から問い合わせが入っています」
射程は国内市場だけではなかった。「世界をにらんだ緻密な市場分析が前提なのです」と有路氏。
日本でのウナギ類の市場は年間12万~14万トン。ウナギが足りないなら、不足分はそっくり、ナマズの潜在市場だ。だから必ず儲かる。
一方、世界を見ると、ナマズは養殖魚で三番目に需要が多い魚で、食べないのは日本人くらい。超メジャーな食材なのだ。その巨大市場へ、脂の乗った、ひときわ美味しいブランドナマズを供給できれば、ヒットは間違いない。
「日本はプレミアムナマズの輸出大国になれる。ナマズの養殖は成長過程の大部分において田んぼの転用も可能なので、米に替わる輸出産物にもなりうるんです」
有路氏は熱く語った。世界戦略をもって、満を持して、ナマズを選択したのだ、と。多くの大学発ベンチャーは、まず「研究ありき」で始まる。優れた研究をビジネスにできないか、と起業する。
だが、近大はその逆だ。まずは市場の有無を見極める。そして、世の中の需要に対処するための研究が、学内のどこにあるのか探す。その上で、市場の要求と研究や新技術とを組み合わせていく。
「必ず儲かる」秘訣とは、研究とビジネスを逆転させたこの発想にあった。
SAPIO2016年9月号
●山下 柚実(やました・ゆみ)/五感、身体と社会の関わりをテーマに、取材、執筆。ネットでメディア評価のコラムも執筆中。最新刊は『広島大学は世界トップ100になれるのか』(PHP新書)。その他『なぜ関西のローカル大学「近大」が、志願者数日本一になったのか』『都市の遺伝子』『客はアートでやって来る』等、著書多数。江戸川区景観審議会委員。
記事を読む
この記事をシェア