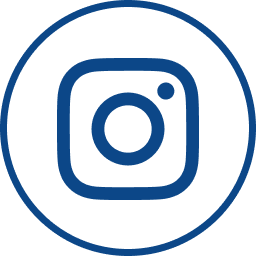2025.10.03
退院した子どもが医師を目指してくれる喜び。「子どもたちが私の先生」と語る小児科医の歩み

- Kindai Picks編集部
3827 View
子どもたちの腎臓病や膠原病、心身症の診療に長年携わり、現在は近畿大学医学部小児科学教室主任教授として多くの子どもと向き合う杉本圭相先生。「病気になる子どもに罪はない」と語り、親子との丁寧な対話を通じて、心と体の健康を支え続けています。自身の医師としての原点から、研究者としての挑戦、そして新病棟での取り組みに至るまで、未来を見据えた医療への思いを伺いました。
この記事をシェア
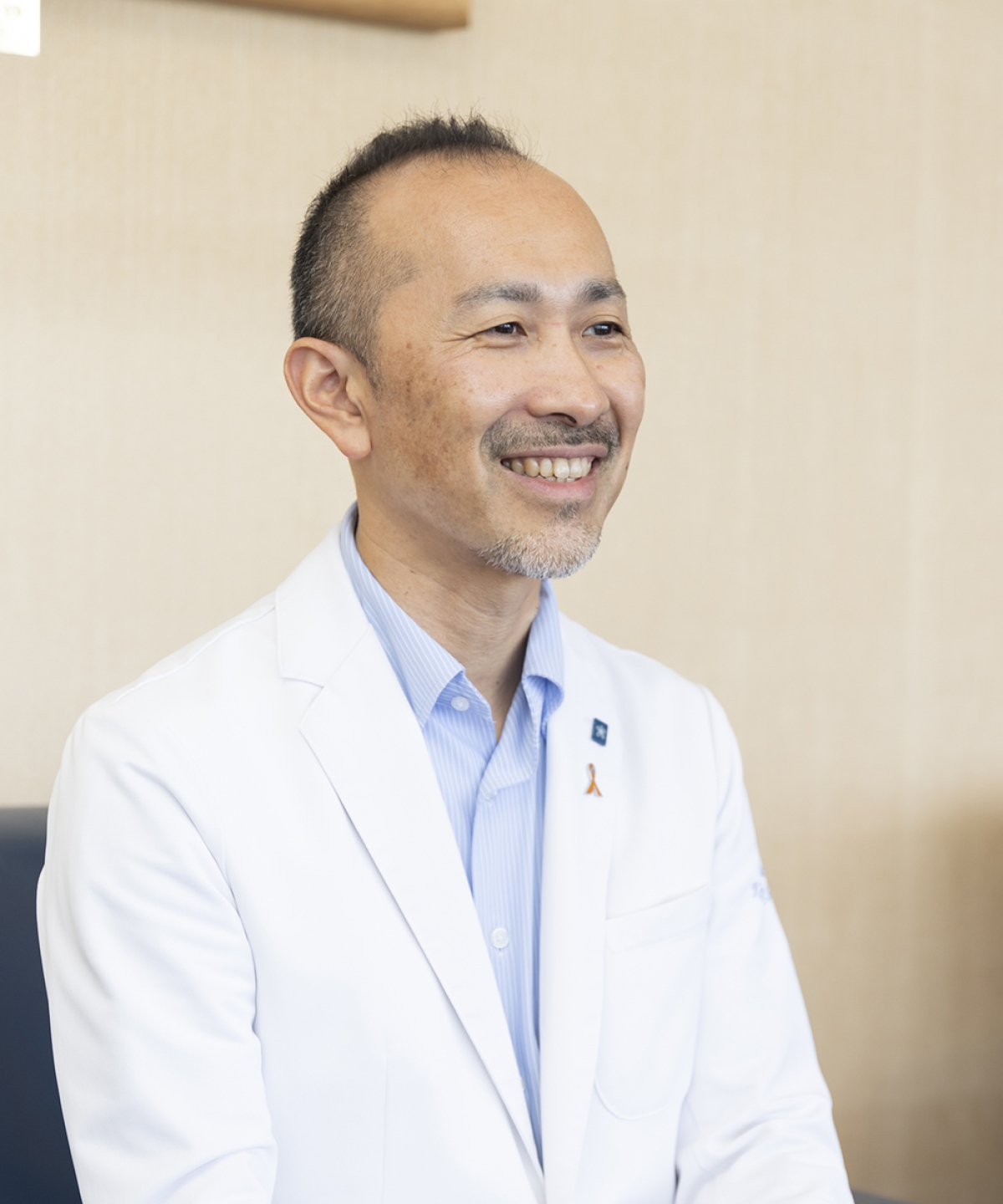
杉本 圭相(スギモト ケイスケ)
近畿大学医学部小児科学教室 主任教授
専門:小児腎臓・膠原病、夜尿症、心身症
静岡県藤枝市出身。平成14年近畿大学医学部医学科を卒業。小児科学教室に入局し、卒後研修を終了。大学院在籍中に、アメリカ合衆国・テネシー州にあるVanderbilt大学腎臓内科でリサーチフェローとして基礎研究に従事し、HB-EGFをはじめとする成長因子や接着因子についての基礎研究を行う。専門は、ネフローゼ症候群、IgA腎症などの小児腎臓領域、全身性エリテマトーデスや若年性特発性関節炎などの小児リウマチ・膠原病、自己炎症性疾患、夜尿症、心身症(不登校児を含む)、起立性調節障害など幅広く診療。近年、小児疾患の多くの分野において、診断をより確実に行うことができるようになり、使用できる治療薬の選択肢も増えたことで、子どもたちや保護者のQOL改善を実感。
母の治療をしてくれた医師に憧れた幼少期。レンガ造りの医学部キャンパスに惹かれて近畿大学に進学
──はじめに、先生が医療の道に進んだ理由をお聞かせください。小学生になる前から「医師になりたい」と漠然と思っていました。母親が肝臓の病気で入院したとき、その治療にあたってくれた医師の姿を見て、自分も将来は人を助けたいという思いが強くなりました。またNHKの大河ドラマ『いのち』で描かれる医師の仕事にも憧れました。しかし父母や親戚に医師はおらず、高校まで成績も秀でていたわけではなかったので、医師になるまでにはかなり苦労しましたね。私は静岡県出身で、関東の大学を中心に受験しましたがなかなか合格できませんでした。3浪目で初めて近畿大学を見学し、レンガ造りのキャンパスに強く惹かれ、「ここで学びたい」と思ったことを覚えています。私は医師になって20年ちょっとですが、近大が私を拾い上げてくれたことで医師人生がスタートしたことに恩義を感じています。
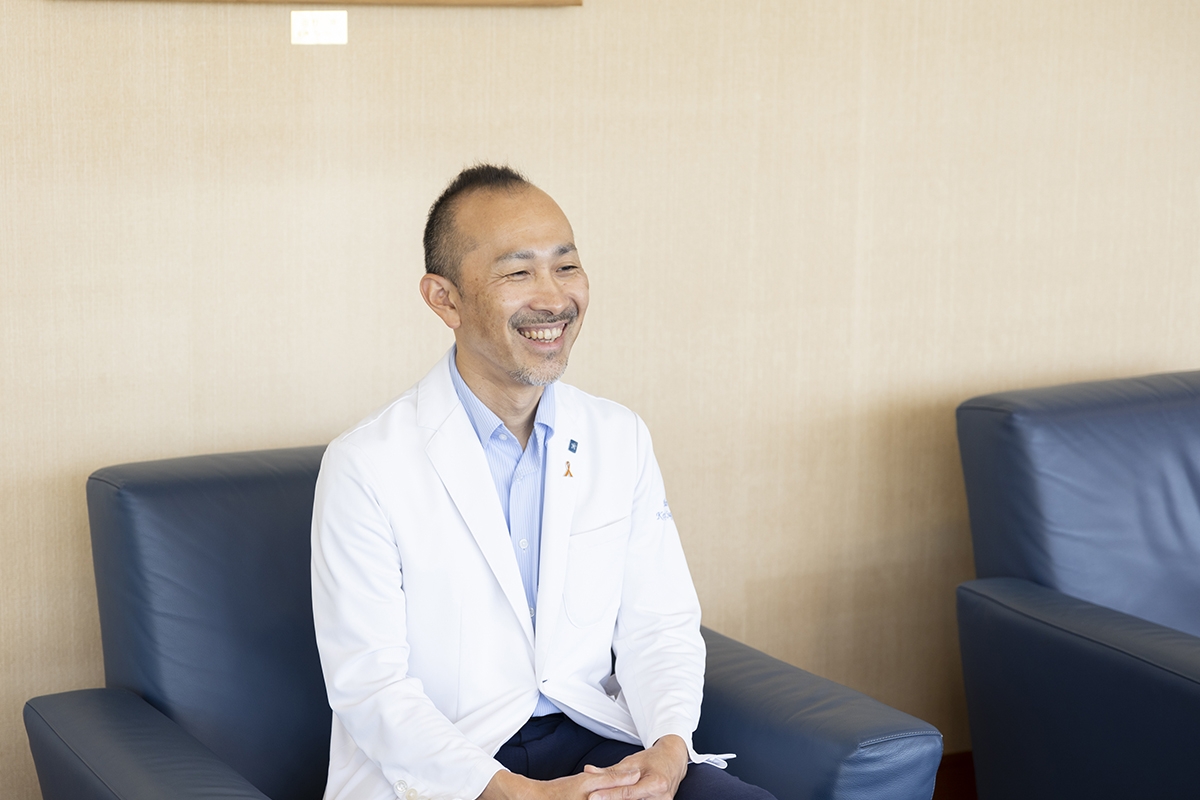
──どのような学生生活を送りましたか?
高校時代の反省から、医学部では真面目に勉強しました。講義はほぼ皆勤で、試験もどれひとつ落とさずに頑張りましたね。また新しいことにも取り組みたかったので、未経験でしたが医学部のラグビー部にも入部し、6年間続けました。足は速いほうだったので「ボールを持ったらとにかく走れ」と言われ、ひたすら走り続ける日々。練習に試合にハードな毎日でしたが、仲間と必死で努力した時間は良い思い出です。勉強と部活、バイトに明け暮れた6年間は、医師として働き続ける上での気力・体力を築く大切な時間となりました。
「小児科医は大変」だからこそ、子どもたちに寄り添う道を選んだ
──小児科を専門にした理由は何だったのでしょうか?未知の領域が多かったことが理由のひとつです。小児の腎臓病や膠原病など、原因が未解明の病気が多く、チャレンジ精神を掻き立てられました。また子どもを病気や虐待などから助けたいという使命感もありましたね。恩師である小児科学教室の前主任教授・竹村司先生からも、「子どもたちとその家族の悩みを共有し、現在、将来ともに副作用に悩むことのない安全な医療を提供すること」が小児科医の使命と教えられました。
──病気に苦しむ子どもを専門に診る小児科医は、他の科に比べてもヘビーな印象があります。
はい、実際多くの人から「なぜ大変な小児科を選ぶのか」と言われました。しかし言い方は難しいですが、大人に比べて子どもの病気には「罪がない」のです。中年期以降に発症する成人病の原因の多くは、本人のそれまでの生活習慣の積み重ねです。それに対して子どもの病気や虐待は、本人の責任ではなく、遺伝や周囲の環境が原因であることがほとんど。「小児科医は大変だからこそ、やりたい」と考えたのはそれが理由でした。医学部を出て近大病院で臨床にあたるようになってからは、生命に関わる重い病気のお子さんから、比較的軽症のお子さんまで、さまざまな子どもたちと向き合う日々を過ごしました。

──大学院に入学してから、アメリカのテネシー州にあるVanderbilt大学の腎臓内科に留学しています。そちらではどのような研究を?
主に「細胞接着」と呼ばれる、細胞同士がくっつき合って臓器を形成するプロセスについての基礎研究を行いました。腎臓病の中には細胞接着がうまく機能しないことが原因で発症する病気があり、そのプロセスを精緻に解明することで、効果的な治療法や薬の開発につなげることが目標です。腎臓病は全身の健康とも深く関わる複雑な領域で、日本に帰国してからも、ネフローゼ症候群(※)など腎臓関連の病気の研究を続けました。その後、腎臓病の診療ガイドライン作成や教科書執筆にも携わり、最近では低出生体重児の腎臓病リスクにも注目しています。2500グラム未満で生まれた子は成人期に腎臓病を発症しやすいことがわかっており、予防策を探っています。
(※)尿中にタンパクがたくさん漏れ出てしまい、血液中のタンパクが減り(低たんぱく血症)、その結果、むくみ(浮腫)が起こる疾患
子どもたちに「決めつけ」は厳禁。かつて診療した子が医療の道に
──現在は主に、どのような子どもを診察していますか?小児腎臓病の子どもと、心身症や思春期の問題を抱える子を半々で診ています。前者では、ネフローゼ症候群や糸球体性腎炎、先天性腎疾患の治療が中心です。心身症では、起立性調節障害や不登校の子どもたちを支援しています。起立性調節障害は、呼吸や体温の調節などを司る自律神経の不調によって、朝起きたときに目まいや立ち眩み、低血圧などの症状が起こる病気です。特に思春期の頃は、自律神経のバランスが崩れることが珍しくありません。
──私の知人の家庭にも、起立性調節障害と診断を受けて、毎日様子を見ながら登校している子どもがいます。
はい、全国的に非常に増えていると思います。ここ数年、日本の小中学校で不登校の生徒が大変増えていることが社会問題となっていますが、その原因のひとつに、起立性調節障害があるのはほぼ確実です。実際には病気が原因なのに、「怠けている」と見なされることで自己肯定感が下がり、親との関係性が悪くなってしまうことも珍しくありません。そうした生きづらさを抱えている子どもだけでなく、その親とも面談して信頼関係を築き、改善に向かっていく取り組みを続けています。
──子どもだけでなく、親とも面談を実施するんですね。
なぜなら小児科の特に心身症では、親子関係を診るのが非常に大切だからです。初診の患者さんには、面談に2時間ほどの時間をとることもあります。最初は親子一緒に話を聞きますが、どちらかが話している間、もう一方がどのような様子で聞いているかをチェックします。その後30分ずつ個別に面接しますが、子どもには「ここで聞く話は君のいのちに関わること以外、親には伝えないから安心して」と約束してから話を聞く。心身症の治療では、親子関係を丁寧に観察したうえで、良い方向に変化を促すことがとても大切になります。
──カウンセリングをする上で気をつけていることは何でしょうか?
子どもに対して、上から目線で「決めつけ」をしないことです。大人からの「あなたはこういう人だ」という決めつけを子どもは一番嫌いますし、決めつけをする大人のことを絶対に信用しません。決めつけるのではなく「君が感じている今の状況、どんな風に周りを捉えているか、教えてほしい」と伝えて、認識を少しずつすり合わせていくのがカウンセリングの基本になります。私は子どもたちより年齢はずっと上ですが、以前から「自分の出会うすべての人は教育者」だと思っているんです。子どもたちと接することで、治療に役立つ気づきを教えられることもよくあります。

──そんな日々の診療の中で感じるやりがいは何でしょうか?
なかなか治らないネフローゼで、約10年間治療に通ってくれた男の子がいました。ようやく10年目に治療の必要がなくなって「もう通院しなくても大丈夫だよ」と伝えたんですが、おとなしい子でそのときは何も言わなかったんですね。ところが、小学校の授業でつくった「12年後の私」という粘土細工の写真を、親御さんが見せてくれたんです。彼がつくったのは、自分が医師として働いている姿でした。
──それは……感動しますね。
はい。高3になった彼はいま、医学部を目指して勉強を頑張っていて、嬉しいことに将来、僕と一緒に働きたいと言ってくれているそうです。彼だけでなく、最近、近畿大学附属看護専門学校の講義に行ったら「先生、私のことを覚えてますか。あのとき、先生に診てもらいました。いまは看護師になるために頑張っています」という方とも出会いました。そんな風に、自分がやってきたことが巡り巡って繋がり始めている、という実感を覚えてきたところです。
50年の節目に感じる小児科医の社会的意義。子どもの健康こそが健全な社会の礎
──近畿大学医学部・病院は、2025年11月に堺市に移転します。移転にともない、小児科ではどんな取り組みをしているのでしょうか?子どもにとって病院というのは基本的に「怖い」場所です。注射や治療で痛みを感じることもあれば、入院すると同時に、それまで営んできた日常生活が断ち切られ、社会から分断されてしまいます。そんな病気と治療の苦しさ、社会からの孤立に苦しむ子たちが、少しでも治療に前向きに取り組む一助となるよう、「社会とのつながり」を実感できる病棟づくりを進めています。このプロジェクトには、近畿大学の文芸学部と経営学部、情報学部の研究室・ゼミ生にも協力してもらい、処置室や病棟のデザインを行いました。
──具体的にはどのような工夫をしているのでしょうか。
中高生の子どもたちは、入院によって勉強に遅れが出ることも不安に感じています。従来の病室は机もなく、勉強に不向きだったので、「ティーンズルーム」という自習室のような部屋を設けました。また「プレイルーム」の中にちょっとした基地のような場所をつくったり、外の空気を感じられるようなスペースも用意しています。情報学部の研究者や学生には、所定の薬を飲むと「クエスト」を進めている感覚になりながら「タスク」が達成できるというアプリをつくってもらい、子どもたちが検査や治療を少しでも楽しめるような工夫を始めています。

子どもたちが夢中で遊べる空間として新病棟に設置したプレイルーム。
 病院であることを忘れるような、思わず注目してしまうデザインに仕上げた処置室などの天井。
病院であることを忘れるような、思わず注目してしまうデザインに仕上げた処置室などの天井。──最後に、少子高齢化が進むこの国で、子どもたちの健康を守ることについて、どのような思いを持っていますか?
2024年の出生数は70万人を切りました。私は第2次ベビーブームの1974年生まれで、3倍近くの出生率でした。近畿大学医学部が設立されたのも1974年で、その50年の節目に自分が関わっていることに、大きな意味があると感じています。近畿大学は実学を大切にするのが教育理念で、経済界にも多数の優れた人を輩出していますが、医療界でも多数の人がこの大学を巣立って活躍しています。一方で少子高齢化が進む中で、医療を支える人が少なくなっていくことも確実です。だからこそ、これから生まれてくる子どもたちや、今いる子どもたちを心身ともに健康な状態で育てていくことが、この国の未来にとって非常に重要だと考えています。子どもの健康を守ることは、大人の健康を守ることでもあり、社会全体が健全で住みやすい国になることにも直結する。そんな思いを胸に、これからも子どもたちを「先生」として学びながら、診療にあたっていきます。
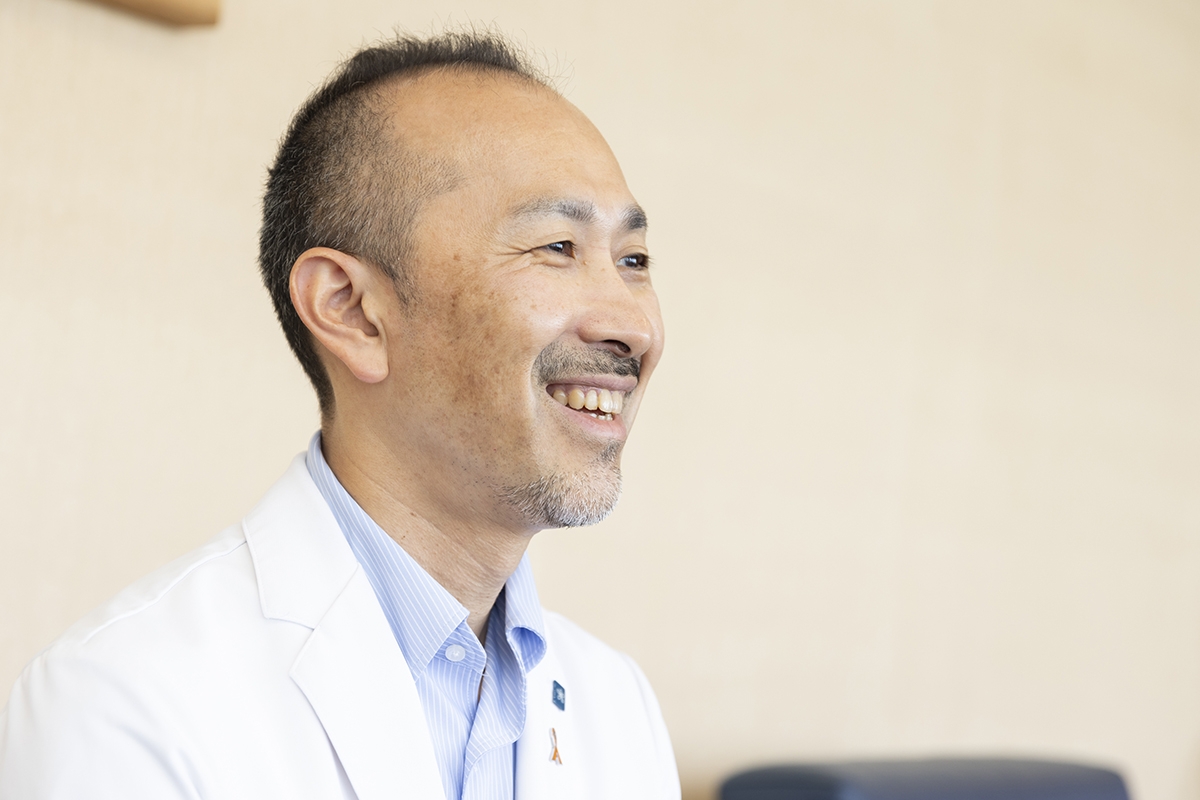
取材・文:大越裕
写真:牛久保賢二
編集:人間編集舎/プレスラボ
この記事をシェア