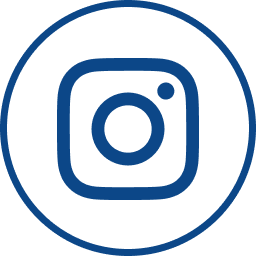2025.10.03
アメリカ横断で育んだ行動力を糧に。宮崎県えびの市・村岡隆明市長“あるもの探し”で地域と人をつなぐまちづくり

- Kindai Picks編集部
896 View
2009年に宮崎県・えびの市長選挙に初当選し、現在4期目を務める村岡隆明市長。「やらずに後悔するより、やって後悔したほうがいい」と語る行動力の原点には、近畿大学在学中に挑んだアメリカ横断バイク旅の経験があります。村岡市長が語るえびの市の魅力や次世代に伝えたい思いについて、お話を伺いました。
この記事をシェア

村岡 隆明(むらおか たかあき)えびの市長
鹿児島県姶良郡湧水町(旧・吉松町)出身。1985年に近畿大学理工学部金属工学科を卒業後、大阪でビークルアドバタイジング社に入社。帰郷後は印刷会社勤務を経て、1999年にえびの市議会選挙で初当選。市議会議員を3期務めたのち、2009年にえびの市長に初当選し、現在4期目を務める。
フェリーでの出会いをきっかけに、アメリカ横断。旅が育んだ行動力の原点
──近畿大学に進学したきっかけを教えてください。父が高校の理系の教員で、よく「金属工学は面白い」と話していたことがきっかけです。金属工学科がある大学を探す中で、推薦入試の時期が早かった近畿大学を選びました。当時は「早く決まれば早く遊べる」と考えていた部分もありましたね。
──村岡市長は鹿児島で生まれ育っていますが、大阪への進学に迷いはありませんでしたか?
まったくありませんでした。父からも「近場に行くな、遠くの大学に行け」と言われていたので、大阪や東京の大学に行く心づもりはできていたのです。入学後、1年目は学生寮で暮らしました。関東出身の学生もいれば、僕の通っていた高校から一緒に入寮した友人もいて、多様なバックグラウンドの仲間と交流できたのがよかったです。風呂もトイレも共同で、門限がある寮でしたが、金網が破れているところから出入りして(笑)。日々活気にあふれていましたね。

当時はお金もなく、寮の仲間がアルバイト先から閉店前に余った餃子を持ち帰ってくるのを皆で夜遅くまで待っていたことなど、思い出は尽きません。今でも当時の仲間とは年に一度ほど集まり、近況を報告し合っています。
──青春の日々が伝わってくるエピソードです。学生時代の思い出で、特に印象に残っていることはありますか?
鮮明な記憶として残っているのは、アメリカをバイクで横断した旅です。きっかけは、帰省のために大阪から鹿児島に向かうフェリーに乗ったとき、世界中を自転車で旅しているというおじさんに出会ったことでした。
おじさんからは「借金してでも海外に行った方がいい」と強く勧められて……30分ほど話しただけでしたが、いきいきと語るおじさんの姿に「行くしかない」と思いました。実家に帰ってすぐに父を説得。アメリカに早速旅立ち、シカゴでバイクを買い、ロッキー山脈を越えてサンフランシスコまで1万キロ以上走りました。
──フェリーでのおじさんとの出会いから一気にアメリカへ……行動に移すスピードがすごいですね!
昔から直感で動くタイプだったのだと思います。インターネットもスマートフォンもない時代で、地図と住所のみを頼りにした旅は、現地に行ってみて初めて分かることだらけでした。情報だけで判断せず、自分の目で確かめることの大切さは、今でも自分の考え方の軸になっていますね。
「自分だけの幸せ」から「地域全体」へ。政治を志した理由
──卒業後はどのような道を歩みましたか?大阪の広告代理店に就職しました。好きだったバイクや車の広告を手がける会社で働けたことはうれしかったです。雑誌広告の制作に加え、サーキットで車を走らせてスポンサーを集める仕事などもあり、現場の最前線に立って働くおもしろさを知りました。
──地元・鹿児島に戻るきっかけは何だったのでしょうか。
父が59歳で急逝したことです。もともと「俺が死んでも帰ってくるな」と言っていた父でした。大阪での仕事にはやりがいを感じていて、離れることに迷いもありましたが、母にはたくさんわがままをきいてもらったこともあり、恩返しがしたいと、帰郷を決めました。
──帰郷後はすぐに政治の世界へ入ったのでしょうか?
いいえ、まずは小林市の印刷会社で9年間働きました。私の故郷は鹿児島県ですが、えびの市に隣接していたこともあり、縁もあってこのときからえびの市に住むことになりました。その間に青年会議所に入り、地域のイベントやまちづくりに携わるようになったことが転機です。青年会議所では、地元をよりよくしたいという熱い思いを持つ方々と出会いました。そこから「自分だけが幸せになればいい」から「地域全体を元気にしたい」という思いへと変わっていったのです。

──その後1999年には、市議会議員に就任しています。立候補したきっかけをお聞かせください。
青年会議所で出会った宮崎3区の国会議員・古川禎久さん(2025年7月時点)の存在が大きかったです。彼が「日本をなんとかしたい」とくり返し話すのを聞いて、その情熱に最初は驚きましたが、本気で政治を志す姿勢に心を動かされていって……僕も「えびの市のためにできることがあるかも」と思い、市議会議員に挑戦しました。
──それからえびの市長になるまでは、どのような経緯があったのでしょうか?
市議を3期務める中で、「提案しても実行できない」という限界を感じるようになりました。ちょうどそのタイミングで議会が解散したため、市長選への挑戦を決意したのです。
「まだ46歳だから、のちの人生で後悔しない行動をしよう」という考えが、市長という立場へ挑戦する覚悟につながったと振り返っています。
水と食に恵まれたまちから、“第2のふるさと”を育てる教育を
──市長として特に注力してきた取り組みを教えてください。観光や移住の推進にも関わる「地域資源の生かし方」と、定住につながる「教育環境の魅力化」の取り組みのどちらも大切にしてきました。
えびの市は鹿児島県と熊本県との県境に位置し、三県の文化が混ざり合う独自の風土があります。霧島山の自然やおいしい水、宮崎牛や米といった食の魅力もある。地元にとっては当たり前に思えるような資源でも、外から見ると非常に価値があるものです。
だからこそ、「ないものねだりではなく、あるもの探し」という姿勢で、今あるものを磨き上げて発信することを意識してきました。
──素敵な考え方ですね。教育分野ではどのような取り組みを?
市内の県立高校が定員割れで統廃合の危機にあった際、市が主体となって学生寮を運営し、教育の魅力化に取り組んできました。現在は全国枠が導入され、約30名の生徒が全国から来てくれるようになっています。
全国的に「子どもを産み育てやすい環境づくり」が求められている中、それだけで出生数が増えるかというと、現実はなかなか難しいところです。外から若い世代を呼び込み、えびの市での学びを経験してもらうことで、このまちを「第2のふるさと」と感じてくれる人を増やしていきます。
実際に、高校卒業後にえびの市の観光アドバイザーとして地域に関わり続けている生徒もいます。教育に力を入れることが、結果的にまち全体の活性化にもつながっていると感じていますね。

──村岡市長の取り組みを伺っていると、「ないものねだりではなく、あるもの探し」という言葉が改めて印象に残ります。
田舎には「何もない」と思ってしまいがちですが、外から見れば魅力的なものがたくさんある。僕自身が“よそ者”としてえびの市に来たからこそ気づけたことも多かったです。
目の前の課題に向き合うだけでなく、10年、20年先にどう評価されるかという視点も持ちながら、地域の価値を見つめ直し、次の世代へつないでいきたいです。
「やらずに後悔より、やって後悔」市政のバトンを渡しながら、挑戦する若者を応援したい
──村岡市長は、次の選挙には出馬しないと表明していますね。はい。長くトップにいると、自分の意見が通りやすくなり、反対意見や自分とは異なる視点が出にくくなっていると感じるようになってきて。そろそろ新しい世代へ引き継ぐのが良いと考え、4期目の当選時点で、次の選挙には出ないと後援会の中で伝えていました。
──今後の活動について、どのように考えていますか?
まずは家族、特に妻への感謝を形にしたいです。16年間、政治に集中してきた分、家族の支えには本当に助けられました。また、ロータリークラブや地域活動などを通じて、地域への貢献を続けたいと思っています。

──近畿大学OBとして、卒業生や在学生、保護者の方々へメッセージをお願いします。
とにかくチャレンジして、その経験を自分のものにしていく姿勢を大切にしてほしいです。行動を起こすことにためらって時間が過ぎていくよりは、まずはやってみること。特に若いうちは、時間的な自由もありますし、失敗してもやり直せます。
僕自身、フェリーで出会ったおじさんとの30分の会話をきっかけにアメリカ横断の旅に出ました。「やらずに後悔するより、やって後悔する」。今しかできないことに思いきって飛び込めば、将来きっと役に立つはずです。
取材:野村英之(プレスラボ)
文:竹内ありす
写真:内藤正美
編集:人間編集舎/プレスラボ
この記事をシェア