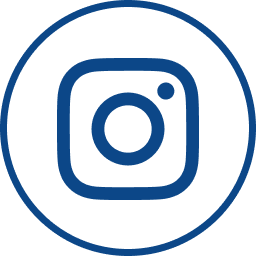2025.10.03
【近大×100年】第3章:母校を職業人の心のふるさとに。学長と校友会長が見つめる、近大の魅力の本質

- Kindai Picks編集部
1327 View
「65歳になり、新しい夢ができた」——2024年、創立100周年を目前に控えた近畿大学の入学式で、松村到学長が発した“I have a dream”の一言は、学びの海へ船出する学生たちにインパクトを残しました。ついにその節目を迎えた近畿大学は、次の100年でどのような役割を果たしていくのでしょうか。松村学長と、校友会の西村松次会長に、将来の展望を伺いました。
この記事をシェア

松村 到(まつむら いたる)
近畿大学学長
1984年大阪大学医学部卒業後、同大学医学部血液・腫瘍内科准教授などを経て、2010年から近畿大学医学部 血液・膠原病内科 教授となる。白血病治療の国内第一人者として、造血幹細胞移植や分子標的療法の研究・診療・教育を牽引してきた。1999年には、日本白血病研究基金 荻村孝特別研究賞を受賞。近畿大学医学部長、副学長を経て、2024年に同大学の学長に就任した。大学全体の研究の推進に尽力するとともに、世界大学ランキング向上に向けた戦略立案の中心を担っている。
教員情報詳細

西村 松次(にしむら まつじ)
近畿大学校友会会長
佐賀県出身。1971年に近畿大学理工学部機械工学科を卒業し、九州電気工事株式会社(現・株式会社九電工※)に入社。福岡支店長、営業技術統括本部長、東京本社代表などを歴任し、会社初の「技術系出身・生え抜き社長」となった。2016年に校友会長に就任し、校友ネットワークの拡充に尽力、全国47都道府県での支部設置を実現した。在学生のキャリア支援などにも注力しており、若手へ熱いエールを送り続ける。
※株式会社九電工は、2025年10月に、株式会社クラフティアに社名変更しました。

石塚 理奈(いしづか りな)
2016年近畿大学文芸学部文学科卒業。東大阪市をホームタウンにするJリーグクラブ「FC大阪」のクラブアンバサダー兼スタジアムMCのほか、大阪府庁公式行事をはじめ各種式典・イベントで司会を務める。また在阪局を中心に、テレビ番組のリポーターなど多岐にわたって活躍。趣味は映画鑑賞、スポーツ観戦。
近大の“次の100年”の礎をどのように築くか、ワクワクしている

「近大×100年」シリーズではこれまで、大阪専門学校と大阪理工科大の統合による近大の誕生、そして医学部の誕生と、教育機関として転換点となった出来事を、当時をよく知る人物のお話を通して振り返ってきました。最終章となる今回は、大学の最高責任者である学長と、全国に拠点を構えるOB組織・校友会のトップがどのような未来予想図を描いているのか、2016年に文芸学部を卒業し、タレントとして活動する石塚さんが深掘りします。
石塚:松村学長といえば、思い出すのが2024年の入学式です。私も司会として参加していたのですが、スピーチで掲げられた“I have a Dream”はとても印象的で……学生たちの心をつかみ、会場がひとつになった瞬間でしたよね!
松村:若い学生たちに私の好きな言葉を贈り、「65歳の私も新しい夢を持っている」と示すことで活力を与えたかったんです。近大を西日本一、いつかは日本一の私立総合大学にするという夢を語りました。
石塚:そして創立100周年を迎えた今、どのようなお気持ちで過ごされていますか?
松村:1925年に創立した本学は、現在は15学部49学科※を擁し、卒業生は59万人を超える総合大学になりました。次の100年に近畿大学をどうやって発展させていくのか、その礎を築きたいと思っています。そこにプレッシャーを感じるというよりは、「これから一体何ができるかな」とワクワクしているんです。近大はあらゆる領域でチャレンジできる可能性がありますからね。
石塚:その挑戦の指標として、世界大学ランキングは意識されていますか?
松村:はい。特に、イギリスの教育専門誌「Times Higher Education(タイムズ・ハイヤー・エデュケーション)」(THE)が公表しているランキングは「教育・研究環境・研究の質・産業界・国際性」を重視しています。これは、近大が目指す大学像と一致しているんです。無理をして上位を追い求めるのではなく、我々が目指すべき方向に着実に歩んでいけば、結果としてランキングにも反映されると考えています。
※2026年4月に看護学部が設置される予定であり、16学部50学科となる。

石塚:独自の研究へ注力する姿勢も、近大らしさですよね。
松村:そうですね。「近大マグロ」や「マンモス復活プロジェクト」など、ユニークかつ社会に役立つ研究成果は、今では近大のカラーとして広く浸透しています。このように、ある領域に特化し、世界レベルまで追究していくスタイルは、今後の近大の発展にもつながるはずです。開学以来大切にしている「実学教育」は、これからも重要な指針です。
医師として感じてきた近大の存在感。その強みを伸ばす「おおさかメディカルキャンパス」設立へ

石塚:ところで、松村学長は大阪大学医学部のご出身ですよね。当時、近大にはどのようなイメージを持っていましたか?
松村:地元から近いこともあって身近に感じていて、勢いのある大学という印象でした。同級生もたくさん進学しましたからね。医学生、そして血液内科の医師としては、近畿大学病院は臨床研究に強いイメージがありました。阪大は基礎研究に強い一方、近大は臨床力が光っていて、ずっと気になる存在でした。ここにも実学の精神が宿っているのだと思います。
石塚: 血液内科という道を選ばれたのはなぜですか?
松村:人の命に関わる医師になりたかったからです。初めはがん治療に関心があったのですが、私が大学を卒業したころは、ちょうど白血病の治療薬の開発が進んでいた時期でした。自分もその分野に関わりたいと思い、血液内科を選びました。基礎研究は40歳くらいまで継続し、近大に来てからは大学院生と一緒に研究を進めてきました。
石塚:「日本国内における白血病治療の第一人者」と評価される松村学長から見て、近大は医療分野でどのような特徴がありますか?
松村:特に目を見張るのは、未承認薬の治験の実績ですね。国内で承認されていない薬を実際に使い、その安全性と有効性を評価するものですが、日本でも有数の実施件数で、近畿圏では圧倒的にナンバーワン。新薬を使った治療を望んで、近大病院までわざわざ来たという患者さんもたくさんいます。
石塚:2025年11月に医学部と大学病院を堺市の泉ケ丘地区に移転するプロジェクトも注目を集めています。
 2025年8月撮影の航空写真
2025年8月撮影の航空写真松村:医学部は近大で8番目に設置された学部です。2024年に設立50周年を迎え、さらに2025年、大きな転機を迎えます。移転先に展開する拠点エリアを「おおさかメディカルキャンパス」と銘打ち、基礎研究と臨床研究の環境を再整備するプロジェクトです。もともと世界レベルだった近大の研究がさらに加速すると期待しています。来年度には16番目の新学部として、看護学部も同一キャンパス内に開設します。
石塚:近畿大学病院は、南大阪エリアでは唯一の大学病院ですよね。世界と地域、両方に貢献できる人材をより多く送り出す場になるといいなと、私も思います。
人と出会い、正しい努力の方法を学んだことがステップアップの基礎になった
 お好み焼き「てらまえ」で昼食をとりながらインタビュー。写真奥から、道とん堀、海遊館、ジャパニーズ
お好み焼き「てらまえ」で昼食をとりながらインタビュー。写真奥から、道とん堀、海遊館、ジャパニーズ石塚:研究や医療分野での躍進はもちろん、卒業生のネットワークが活発なのも近大の魅力ですよね。その意味で、卒業生からなる校友会が担う役割は大きいと思います。近大校友会とはどのような組織か、あらためて教えていただけますか?
西村:校友会は、卒業生同士の交流を深めてネットワークをつくることで、会員の活動の充実、ひいては母校の発展を図る組織です。幅広い年代が参加できるイベントを開催し、大学に関する情報発信にも取り組んでいます。大学を卒業すると自動的に入会する形を取っており、2024年、47都道府県すべてに支部を設置することができました。全国の大学の類似団体と比べてみても、かなり精力的な組織だと自負しています。
 近畿大学校友会が主催するビジネス界で活躍する卒業生と在学生との交流イベント「KINDAIサミット2024」の様子
近畿大学校友会が主催するビジネス界で活躍する卒業生と在学生との交流イベント「KINDAIサミット2024」の様子石塚:近大が全国各地に卒業生を輩出してきた、という裏付けでもありますね。西村会長自身は近大に入学されてから卒業、就職されて、現在に至るまでどのような軌跡をたどってこられたのですか?
西村:実は私は、地元の工業高校を卒業してから一度、就職をしているんです。しかし、この仕事でよかったのかな? と疑問を抱えていた。そこで「大学に行って学び直そう」と決心して入ったのが近畿大学でした。佐賀から移り住んでの進学でしたが、この選択は私の人生にとって大きな転機になりました。
石塚:近大での学びがどのような変化を与えたのか、気になります……!
西村:たくさんの人に出会い、「自分に合った仕事はどんな仕事か、それをどうして見つけるかが大切だ」と感じ取りましたね。大学を卒業して就職するときには、過去の教訓を生かし、このことをよく考えながら進路を選びました。それ以来、九電工一筋。努力はもちろん大切ですが、その前に「何を努力すべきか」と考えることが重要なんです。
石塚:着実に実績を積み上げ、ついには地元企業のトップまで行き着いた、という西村会長が経験されたステップ自体が、その学びの価値を物語っていると感じます。やはり初めから高い志があったのですか?
西村:それが、初めは「課長になればいいな」と思っていたんです(笑)。ただ回ってきたチャンスは逃さず、自分に正直に手を挙げ、目の前のことを頑張ってきた。もちろん人との出会いに恵まれ、運が良かった部分もありますが、やはり努力の仕方という基礎を築けた大学時代は有意義でした。
石塚:「やりたいことが見つからない」と嘆く学生や若手社会人もいる中、西村会長の経験談に救われる人は少なくないはずです。そんな後輩たちにアドバイスはありますか?
西村:夢がないことを焦る必要はありません。私もゴールがわかっていたわけではありませんから。むしろそういう人こそ「近大に入ってよかった」と思ってほしい。近大での経験は社会に出ても生きるし、校友会という組織があり、そこに仲間がいる。手を差し伸べてくれたり、相談に乗ってくれたりする人は案外身近なところにいるものです。それこそ、校友会を積極的に“利用”して出会いにつなげてもらいたいですね。

大学と校友会の連携を強化すれば、教育の質は高められる
石塚:出会いを大切にしてきた西村会長が、現在では卒業生を応援する立場にいらっしゃるのはドラマチックですし、説得力がありますね。松村学長は校友会の活動をどのようにご覧になっていますか?松村:大学側も、就職相談やインターンシップの窓口として校友会を頼りにしています。学生の出身地の割合を見ると、もちろんキャンパスの集まっている近畿圏からの入学生が多い傾向はあるのですが、今や全国から学生が集まってきてくれています。彼らが地元に戻って就職する場合、校友会の支部が近くにあるのとないのとでは大違い。大学としても、卒業生との接点になるのでとてもありがたいです。卒業生にとっては、よりどころとなる基地のようなものだと思います。

石塚:社会で活躍している先輩から直接話を聞くことは、それこそ夢が定まっていない学生にとって、貴重な手がかりになりますね! 会長としては、校友会活動における今後の課題は何だと捉えていますか?
西村:私は現在5期10年目で、全国各地の支部を回っていますが、活性化できる余地はまだまだあると感じます。まずは、校友会は全卒業生を対象とする組織であることを在学生に広く認識してもらう必要があると考えています。そのためにも、在学生が気軽に参加できるイベントの企画により力を入れていく予定です。また、学生にとっては身近で影響力の大きいゼミの先生方にも、校友会のイベントに参加していただきたいと思っています。

松村:私たち教職員も、校友会との連携をもっと強めたいです。社会で活躍する先輩の声が加われば、実学教育の質もアップデートされますし、卒業生にとっては、母校や後輩の活躍を身近に感じられる機会にもなります。
西村:近年は、うれしい変化も感じています。特に関東エリアで活動が活発になっているんですよ。校友会リーダーズクラブが毎年主催している新卒業生歓迎会でも、女性参加者の増加を実感しています。私が就職したころは、近大卒の先輩や仲間はなかなか見つけられませんでしたからね。
松村:学生・校友会員・教職員、この三者の関係を強固にし、全員にとってより良い循環を生み出していきましょう!
職業人のふるさととして、挑戦を応援し続けたい
石塚:松村学長は大学運営においてどのような点に重きを置いていますか?松村:第一に、学生の未来の可能性を広げ、それを実現できる大学でありたいと考えています。そして、社会に貢献できる人材を育成し続けていきたいと思っています。在学生たちもいつかは旅立つわけですが、生まれ育ったふるさとを思い出すように、職業人としての心のふるさとは近畿大学だと思ってほしい。その絆を途切れさせないためにも、卒業後は校友会の活動に参加してもらえるとうれしいですね。学生の人生に実りを増やす大学になるためには、校友会との協力は不可欠です。

石塚:私は近大のことを人に話すとき、まさに「心のふるさと」と紹介しています! 卒業生の中でもキャンパスに“里帰り”する機会が多い方だと思います。それでも戻ってくるたびに施設や研究成果など、新しいトピックがあって「また進化してる!」とうれしい気持ちになるんですよね。
西村:志願者数も、2024年まで11年連続で日本一でしたよね。それだけ多くの人が入りたいと思ってくれているのが誇らしいですよ。後輩たちがそんな大学にしてくれたんですね。
大学がふるさとならば、校友会は家族ともいえます。困ったら頼れるし助け合える、そんな温かい輪を広げていきたい。社会に目を向けると、企業とのミスマッチによる早期退職が取り沙汰されていますが、社会人と学生の交流が密になれば、そのような問題の解決にも貢献できると思うんです。
松村:近大では、学生起業を支援するプログラム「KINCUBA」にも力を入れています。起業家の先輩たちがメンターとして学生の指導にあたっていますが、近大卒業生も多数参画してくれています。キャリアの多様性をリアルに示すことができるのも、我々ならではです。
石塚:KINCUBAは、100社創設の目標を前倒しで達成したというニュースも話題になりましたよね。先生方も卒業生も、それぞれの強みを生かして活躍している姿を見ると、私も夢を持たせてもらえるし、そのたびに「頑張ろう」とあらためて思わされます。お二人とこのようにお話しさせていただけたことも、私や読者の今後につながる、ひとつの種を与えてくれたはずです。本日はありがとうございました!
取材:トミモトリエ
文:山瀬龍一
写真:牛久保賢二
編集:人間編集舎/プレスラボ
この記事をシェア