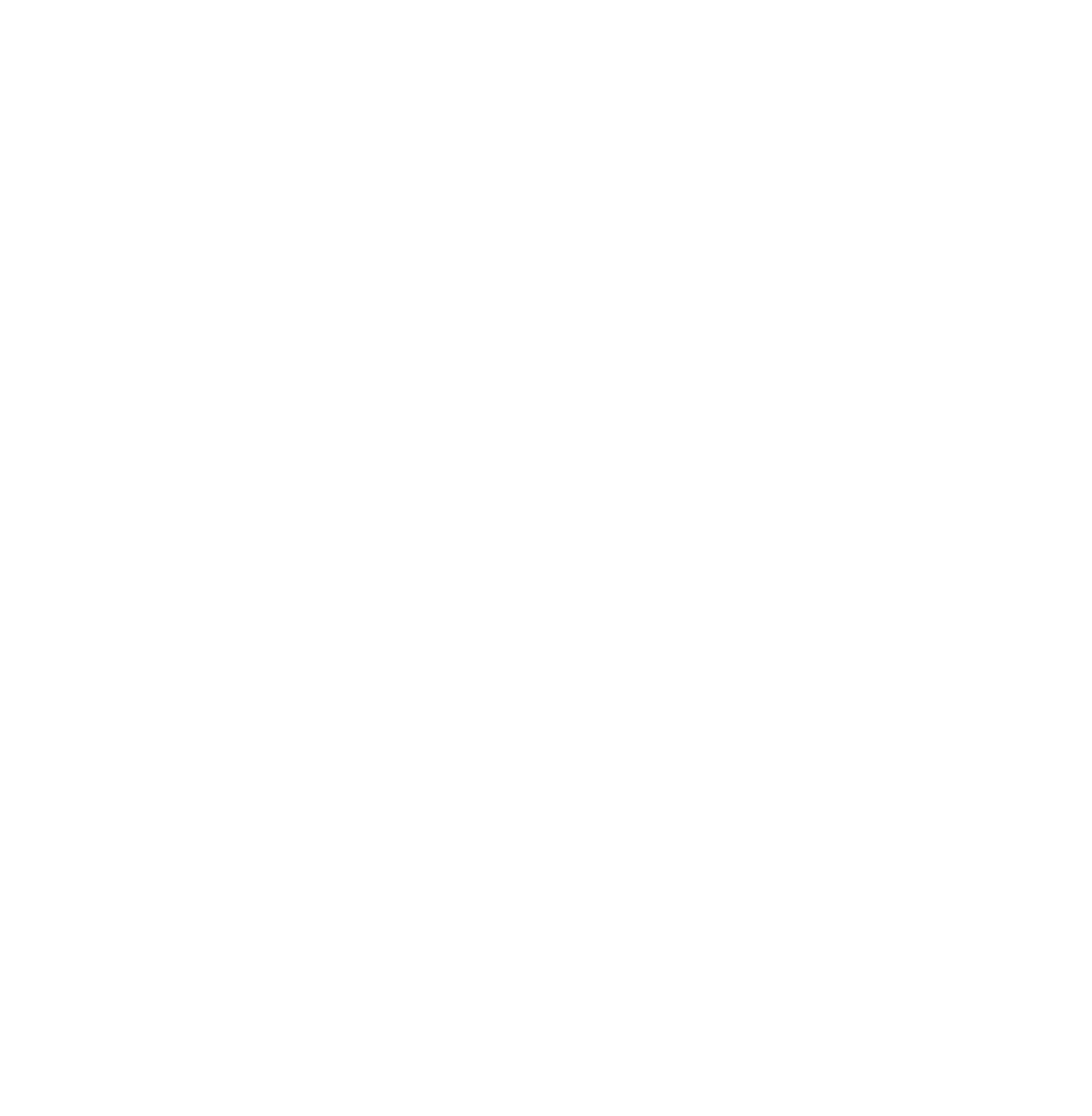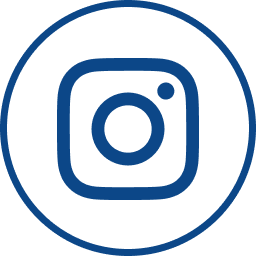2016.01.30
手記 『あの日』 が明らかにした「不都合な真実」

- Kindai Picks編集部
7609 View
STAP細胞事件の当事者である小保方晴子さんが出版した手記「あの日」。
その真の意味と、受け止めるべき教訓について、疑義発覚当時から多くのメディアで本件の解説をしている榎木英介氏(近畿大学医学部病理学教室講師)が分析した。
この記事をシェア
手記は“その日”に出版された
2016年1月28日STAP細胞論文の不正事件を引き起こした小保方晴子氏が、手記「あの日」を出版した。
弁護士を通じたコメントでした動向が分からなかった小保方氏が、沈黙を破り何を語るのか。1月28日はちょうど2年前にSTAP細胞の論文の記者会見を行った日だ。出版は極秘に準備され、この日を狙って発売されたのだ。
発売日の午前0時。電子書籍版を直ちにダウンロードして読んでみた。
自己弁護の本
自己弁護の本だった。STAP細胞論文に問題があることを認めつつ、それがミスや不注意であったと述べ、意図的ではなかったと述べている。さらに、STAP細胞なるものがES細胞由来であった点は、指導者の若山照彦博士(現山梨大学教授)が行ったものであることを強くほのめかす。
若山博士の関与に関しては、ある程度説得力があり、若山博士の釈明が必要になると思う。しかし、STAP細胞の論文に関する疑義は多数あるのにも関わらず、説明しやすいものだけをピックアップしており、その姿勢に疑問が残る。問題が多々指摘された博士論文も、慌てて草稿を製本してしまったためと述べるが、説得力がない。
このように小保方氏の説明は納得いくものではない。包み隠さず語ってくれれば、手記は今後の教訓になると思っていただけに、残念だ。
しかし、その点を差し引いても、手記からはSTAP細胞事件が起きた背景が読み取れる。
利益に群がる組織文化
まず言えるのは、小保方氏に大きな問題があるとしても、小保方氏を利用しようとし、小保方氏一人に責任を押し付けようとした人たちがいるということだ。
小保方氏の研究が有望だとわかるや、様々な人たちが関わるようになり、権利を主張するようになる。小保方氏をユニットリーダーに採用し、組織あげてSTAP細胞論文を完成させようとする。研究規模は大きくなり、小保方氏が論文の内容をコントロールできなくなる。小保方氏に乗っかって、利益を得ようとした人々、組織の存在がみえる。
理研と早稲田の過ち
疑義発覚後の理化学研究所の対応は、明らかに不適切だった。疑義が発覚した後、きちんとした調査を行わず(若山博士がすでに理化学研究所から転出していたという点が大きいが)、幹部がメディアに情報をリークし、小保方氏に責任を押し付けるようになる。手記が赤裸々に描写するように、プライベートまで暴かれ生活することさえままならない状態になった小保方氏を守りきれていない。
早稲田大学も同様で、小保方氏と同程度に問題のある博士論文を提出した人たちはお咎めがなく、小保方氏一人が博士号を取り消された。
小保方氏が関わった組織にしてみれば、小保方氏一人を「悪者」にしてしまえば、責任を回避できるし、所属する人たちを守ることができる。痛みを伴う構造改革もやらなくてよい。排除の論理が働いて当然とも言える。
「不都合な真実」
小保方氏より悪質な研究不正は多々あるわけで、なぜ小保方氏だけが、かくも苛烈な報道被害、バッシングに遭わなければならないのか、合理的な理由はない。もちろん不正は不正だが、小保方氏は刑法犯ではない。本来は科学コミュニティの内部で粛々と処理すべき問題だったのに、それができなかったので、こんなことになったのだ。
これでは、小保方氏が「なんで自分ばっかりが…」と思う理由は分からないではない。手記が明らかにするのは、こうした「不都合な真実」だ。手記は小保方氏の怒りの結晶なのだ。
科学コミュニティへの教訓
私たちはこの手記から何を学ぶべきか。
研究不正が発生したら、早急に証拠保全をし、あとから検証可能なようにすべきだ。STAP細胞事件では、細胞やノートを含めたデータ、記録などが散逸し、全容が解明できなかった。だから、関係者がメディアで批判合戦を繰り広げるという異様な事態になったのだ。早急な調査と証拠保全が行えれば、笹井芳樹博士が亡くなることはなかったかもしれない。
また、一部に責任を押し付けようとする圧力に対抗できる仕組みを考えるべきだ。岡山大学の事例で見え隠れするように、内部調査だけでは、どうしても組織防衛が先に立ってしまう。外部の機関の関与による、公正な調査を担保できる仕組みを早急に作る必要がある。
研究不正はたった一人の悪意だけでで行えるものではない。研究者教育、倫理教育、共同研究者の関与など、防げるポイントは多々ある。また、研究不正を誘発する過度に競争的な環境など、構造の問題も大きい。
STAP細胞事件のようなことが自分たちの施設で起きたらどうなるかを考えてみてほしい。研究不正の取り組みでは比較的先進的だったといわれる理研でさえ、あのような後手後手の対応になってしまったのだ。
我々大学関係者も含め、科学コミュニティは、いち研究者が手記で思いを述べるに至ったという異常な事態を引き起こしたことを大いに反省し、自らの「不都合な真実」を直視し、行動することが求められている。
著者
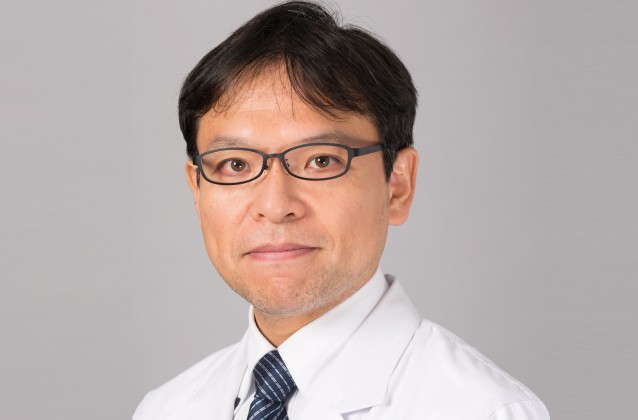
榎木英介(えのきえいすけ)
近畿大学医学部附属病院臨床研究センター講師(病理学教室、病理診断科兼任)
1971年横浜生まれ。1995年東京大学理学部生物学科動物学専攻卒。同大学院進学(指導教官:総合文化研究科浅島誠教授)。博士課程中退後、神戸大学医学部医学科に学士編入学。医学の学業とともに、山村博平教授(現名誉教授)のもとで生化学の研究を行う。2004年卒業。医師免許取得。2006年博士(医学)。2009年神戸大学医学部附属病院特定助教。兵庫県赤穂市民病院にて一人病理医として勤務の後、2011年8月からは近畿大学医学部病理学教室医学部講師。2015年4月から現職。病理専門医、細胞診専門医。近著は「医者ムラの真実」(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、「嘘と絶望の生命科学」(文春新書)ほか
記事を読む
この記事をシェア